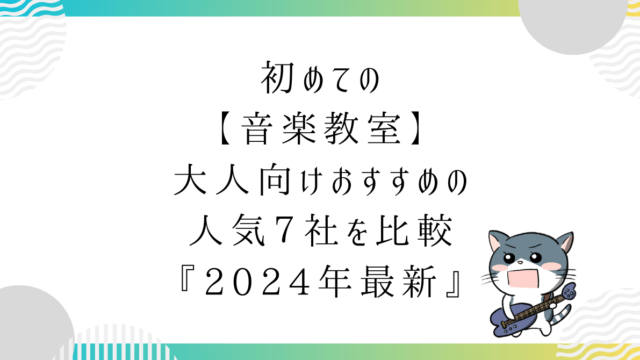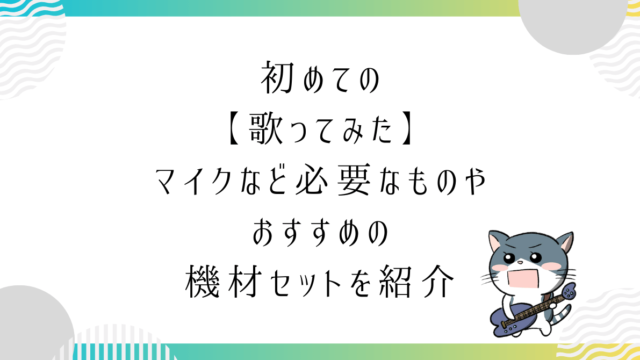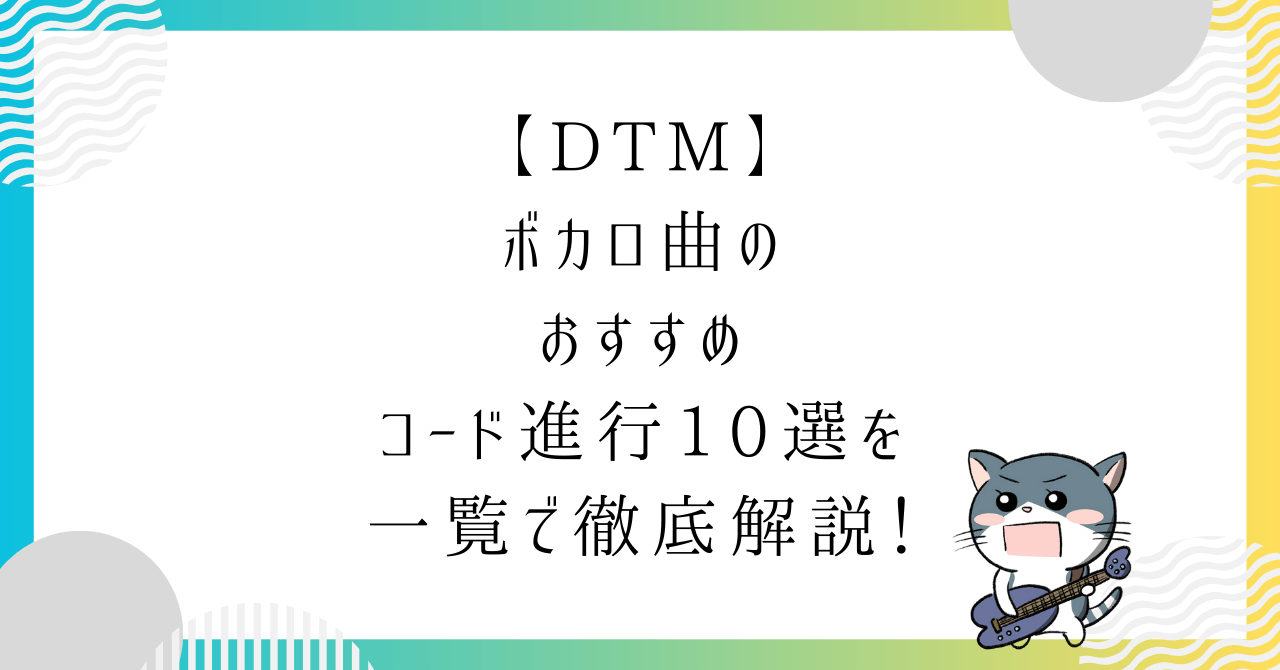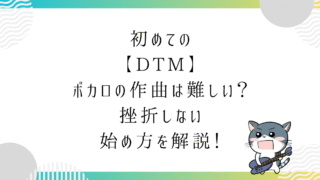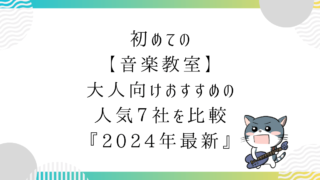「作ったボカロ曲、なんだかパッとしない…」「もっとセンス良くしたいけど、どうすれば?」

この解説記事では、ボカロ曲をワンランクアップさせる、おしゃれなコード進行を10パターン厳選してご紹介します。 音楽理論が苦手でも大丈夫。それぞれのコード進行がなぜ「おしゃれ」に聴こえるのか、その秘密を具体的なボカロ曲の事例を交えながら、徹底的に解説していきます!
ありきたりなコード進行から卒業し、聴く人の心を惹きつける魅力的な楽曲を生み出すためのヒントが満載。もう「良い曲が作れない」なんて悩むことはありません。
「もっと本格的にDTMを学びたい」「一人で悩まずにプロの指導を受けたい」そう感じた方には、DTMスクールという選択肢もおすすめです。体系的な知識と実践的なスキルを効率良く習得することで、あなたの音楽制作はさらに加速するでしょう。
\DTMの情報が沢山!上達も早くなる!/
🎹 DTM・ボカロ曲を格上げする「おすすめコード進行」応用テクニック一覧
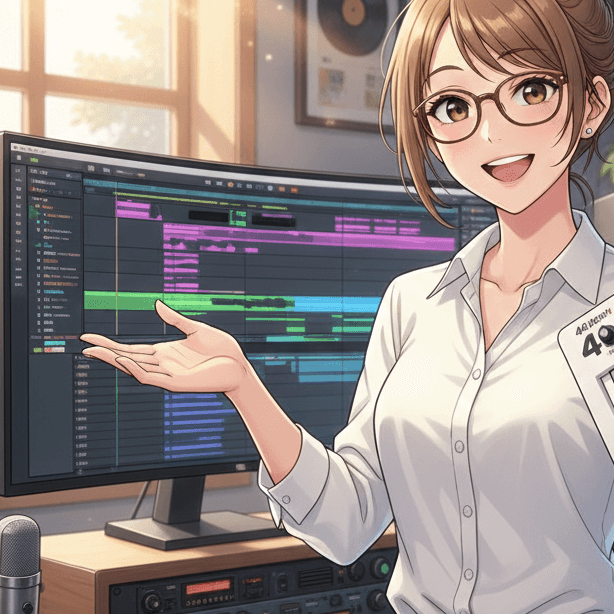
| No. | テクニック名 | 主な効果 | 具体的な使用コード例(Cキー) | ボカロ曲の事例(傾向) |
| 1 | 代理コードの活用 | 洗練、浮遊感、ジャジーな響き。定番進行に「ひねり」を加える。 | 王道進行(C-G-Am-F)のG7をBm7-5に置き換え | バルーン、GUMIのJ-POPテイスト曲(奥行きと透明感) |
| 2 | カノン進行応用 | ドラマティックな緊張感、切なさの倍増。 | G#dim(ディミニッシュコード)をAmの直前に挟む | 「からくりピエロ」「メルト」(感情の揺らぎ、叙情性) |
| 3 | 分数コード(オンコード) | 浮遊感、都会的な洗練。ベースラインを滑らかに動かす。 | C – G/B – Am – G/F# – F(下降するベースライン) | 「シャルル」「Calc.」(独特の疾走感、複雑な響き) |
| 4 | ノンダイアトニックコード | 意外性、ハッとさせる驚き、感情のコントラスト。 | Fm(サブドミナントマイナー)やE7(セカンダリードミナント) | 「乙女解剖」「ロキ」(影のある美しさ、中毒性) |
| 5 | 短調曲にメジャーコード | 悲しみの中に希望の光、力強い高揚感。 | 短調曲の終わりに同主長調のIメジャーコードで解決(ピカルディの三度) | 「劣等上等」「砂の惑星」(力強さ、ドラマティックな展開) |
| 6 | クリシェ(Cliché) | 疾走感、叙情感、ドラマティックな推進力。ベースラインの段階的な動き。 | C – G/B – Am – Am/G#(ベースラインの半音下降) | 「心拍数#0822」「ハッピーシンセサイザ」(感情の深まり、心地よい推進力) |
| 7 | 循環コードの応用 | 中毒性、安定感、無限ループ。飽きさせない緩やかな盛り上げ。 | C – G – Am – Em – F – C – Dm7 – Gを繰り返し、リズムやボイシングを変化させる | 「DECORATOR」「千本桜」(グルーヴ感、多幸感) |
| 8 | テンションコード | ジャジー、大人っぽい、透明感のある洗練された響き。 | Cmaj7(9)、G7(13)、Fmaj7(#11)など | 「プロトディスコ」「夜明けと蛍」(都会的なクールさ、繊細な世界観) |
| 9 | 転調(Modulation) | 楽曲の展開力アップ、クライマックスの高揚感、雰囲気の急変。 | サビで半音上に転調 / 同主調(Am→A)に転調 | 「シャルル」「脳漿炸裂ガール」「千本桜」(楽曲のテンション加速) |
| 10 | 意外なコード展開 | 予測不能な驚き、オリジナリティ。セオリー外の自由な発想。 | A♭maj7 – D♭maj7やディミニッシュコードの連続など、予期せぬ解決 | 「ウミユリ海底譚」「アンノウン・マザーグース」(幻想的、実験的サウンド) |
【実践!】ボカロ曲で使えるおしゃれなコード進行10選を詳しく解説
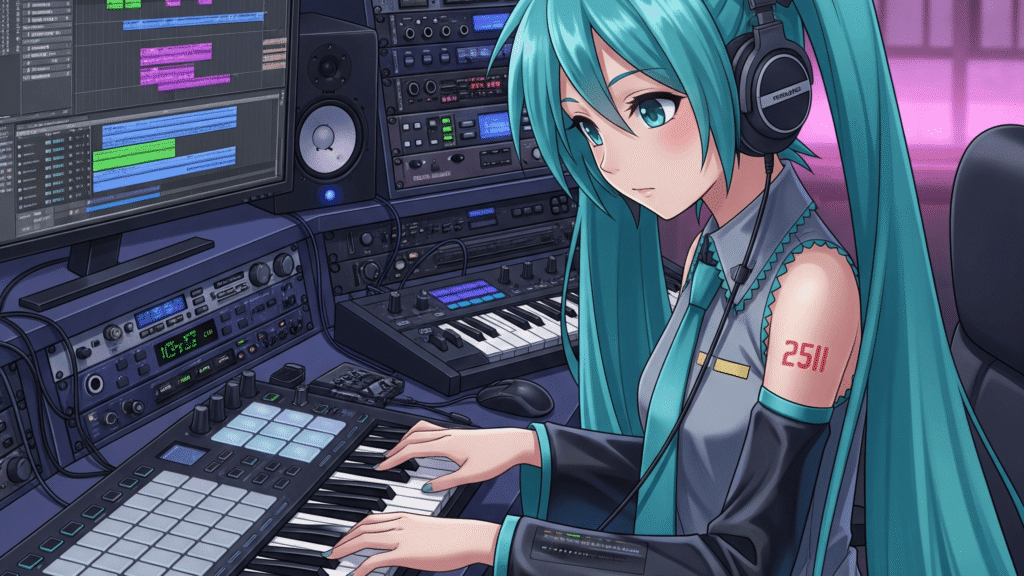
* 1. 王道進行をもっと魅力的に!代理コードで彩る
* 2. 切なさ倍増!あの人気曲で使われる「カノン進行」応用術
* 3. 浮遊感を出す!分数コードの魔法
* 4. 意外性でハッとさせる!ノンダイアトニックコードの活用
* 5. 短調曲に光を!メジャーコードを効果的に使う方法
* 6. 疾走感と安定感!クリシェでドラマティックに
* 7. 憧れのあの曲も!循環コードで無限ループ
* 8. ジャジーな響きをプラス!テンションコードで彩る
* 9. 転調で広がる世界!ボカロ曲の展開力を上げる
* 10. コード進行に「ひねり」を加える!意外なコード展開お待たせしました!ここからは、あなたのボカロ曲をグッと魅力的にする、実践的なおしゃれコード進行を10パターンご紹介します。ただコードを羅列するだけでなく、それぞれのコード進行がどんな雰囲気を作り出すのか、なぜおしゃれに聴こえるのか、そしてどんなボカロ曲に合うのかを具体的に解説していきますね。
音楽理論に詳しくなくても大丈夫。譜面と簡単な解説を交えながら、一つひとつ丁寧に見ていきましょう。これらのテクニックをあなたのボカロ曲に取り入れることで、きっと今までとは違う、聴く人の心を惹きつけるサウンドが生まれるはずです。
1. 王道進行をもっと魅力的に!代理コードで彩る
J-POPでもおなじみの「カノン進行」や「王道進行」は、安定感があって耳馴染みが良いですよね。でも、それだけだと少し物足りなく感じることも。そこで登場するのが代理コードです。
代理コードとは、あるコードと同じような機能を持つ別のコードのこと。これを使うことで、定番の進行にちょっとした“ひねり”を加え、聴き慣れたコード進行が新鮮で洗練された印象に生まれ変わります。
具体的な使用例:
最もよく使われるのが、キーのドミナントコード(V7)の代理です。例えば、CメジャーキーのG7(ソラシドレミファ)は、次にC(ドミナント解決)へ進むという強い特徴があります。このG7の代理としてよく使われるのが、**Bm7-5(Ⅵマイナーセブンフラットファイブ)やD♭maj7(サブドミナントマイナーの代理)**などです。
- G7の代わりにBm7-5を使う例: C – G7 – Am – Em (王道進行) →C – Bm7-5 – Am – Em
Bm7-5を使うと、G7が持つ力強い解決感とは異なり、より浮遊感のある、おしゃれでジャジーな響きになります。特に、バラードや落ち着いた雰囲気のボカロ曲で、サビの頭や盛り上がる部分に使うと、聴き手にグッとくるような洗練された印象を与えられます。 - F(サブドミナント)の代わりにDm7を使う例: C – G – Am – F (王道進行) →C – G – Am – Dm7
Fコードの代理としてDm7を使うと、同じサブドミナントの機能は保ちつつ、より軽やかで都会的な響きになります。王道進行が持つ親しみやすさを残しつつ、少しだけ大人っぽい雰囲気を加えたい時に有効です。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
代理コードは、多くのボカロ曲で意識的、あるいは無意識的に使われています。特定のコードを代理コードに置き換えることで、原曲の雰囲気を保ちつつ、より奥行きのあるサウンドを実現しています。
具体的な楽曲名を挙げるのは難しいですが、例えばGUMIの楽曲や、バルーンさんの楽曲など、J-POPテイストの強いボカロ曲では、王道進行を基本としつつも、随所に代理コードを挟み込むことで、聴き飽きさせない工夫が凝らされています。特に、コード進行に少し切なさや透明感を加えたい場合に、代理コードが効果的に使用されることが多いです。
2. 切なさ倍増!あの人気曲で使われる「カノン進行」応用術
「カノン進行」は、Pachelbelのカノンで有名なコード進行で、一般的には「C – G – Am – Em – F – C – F – G」のような形を指し、その流れるような美しさと切ない響きが特徴です。多くのJ-POPやボカロ曲でも頻繁に使われ、聴く人の心を掴みます。しかし、そのまま使うだけでは定番すぎてしまうことも。そこで、さらにその感情を深める応用術をご紹介します。
具体的な使用例:
カノン進行に「ひねり」を加えることで、よりエモーショナルな響きを生み出すことができます。
- ディミニッシュコードを挟む: 定番のカノン進行の途中に、**ディミニッシュコード(減三和音)**を挟むことで、一瞬の緊張感や不安定さを生み出し、その後の解決感をより際立たせることができます。
例:C - G - Am - Em - F - C - F - G→C - G - Am - G#dim - F - C - F - G
このG#dim(Gシャープディミニッシュ)は、Am(Aマイナー)へ解決する手前に挟むことで、次のコードへの期待感を高め、よりドラマティックな響きを作り出します。特にバラード曲や、感情が揺れ動くシーンで使うと、聴き手に強い印象を与えられます。どこか妖艶で、不安げな雰囲気を演出したい時にも有効です。 - 特定のコードのボイシング(コードの構成音の並び方)を変える: 同じコードでも、音の並び方を変えるだけで印象が大きく変わります。例えば、カノン進行の途中の
EmやAmで、ベース音を動かさずに上声だけを変化させる(インヴァージョンやオープンボイシングにする)ことで、より広がりや奥行きのあるサウンドになります。- 例:C – G – Am(C/A) – Em(B/E) – F – C – F – G 特に、ベースラインを半音階で下降させるようにボイシングを変える「クリシェ」の要素を取り入れると、カノン進行により切なさや叙情感が加わります。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
カノン進行は非常に多くのボカロ曲で使われていますが、その中でもアレンジが加えられている楽曲は数多く存在します。
「からくりピエロ」 (40mP feat. 初音ミク): この曲もサビなどでカノン進行に似たコード進行が登場しますが、その中でディミニッシュコードに近い響きや、特定のコードのボイシングに工夫が見られます。特に、歌詞の切なさと相まって、コード進行が感情をより一層引き立てる役割を果たしています。
「メルト」 (ryo feat. 初音ミク): 言わずと知れたボカロの代表曲ですが、サビの一部などでカノン進行に準じたコード進行が使われています。特に、その進行の中でベースラインの動きやコードの響かせ方に工夫が凝らされており、聴き手に強い感情を呼び起こします。完璧にカノン進行そのものではなく、その骨格をベースに、要所で代理コードやテンションコードが織り交ぜられているため、聴き飽きない洗練された響きになっています。
3. 浮遊感を出す!分数コードの魔法
コードにスラッシュ(/)が入っているのを見たことがありますか?それが**分数コード(オンコード)**です。例えば、「C/G」は「Cコードだけど最低音はG」という意味で、「C on G(シー・オン・ジー)」と読みます。これは、コードの構成音とベースの音が異なる場合に用いられる表記方法です。
この分数コードを使うと、ベースラインが滑らかに動き、フワフワとした浮遊感や、都会的で洗練された響きを生み出せます。おしゃれなカフェミュージックのような雰囲気を出したい時や、夢幻的な世界観のボカロ曲にぴったりです。
具体的な使用例:
分数コードは、特にベースラインを効果的に動かしたい時に威力を発揮します。
- 下降するベースライン(クリシェ): コードのトップノートや構成音はあまり変えずに、ベースラインだけを半音または全音で下降させていくことで、非常に美しい「なめらかさ」と「浮遊感」を演出できます。
例:C - G/B - Am - G/F# - Fこの進行では、ベース音がCからB、A、G#(F#)と下降していくことで、聴き手に心地よい浮遊感と進行感を与えます。特にバラード曲や、しっとりとした雰囲気の楽曲で、サビの頭や感情が変化する部分に使うと、聴き手の心を惹きつけます。 - ペダルポイント(持続低音): コードは変化するのに、ベース音はずっと同じ音を鳴らし続けるという使い方もあります。
例:C/G - Dm7/G - G7/G - C/Gこの場合、ベース音は常にGを保ちながら、上部のコードだけが変化していきます。こうすることで、独特の浮遊感と安定感が同時に生まれ、夢幻的でアンビエントな雰囲気を作り出すことができます。ボカロ曲で神秘的な導入部や間奏に使うと効果的です。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
分数コードは、特に洗練されたサウンドや独特の浮遊感を求めるボカロPに愛用されています。
「シャルル」 (バルーン feat. flower): サビなどで分数コードが使われている箇所があり、楽曲に独特の疾走感と浮遊感を同時に与えています。特に、コードの響きに深みと複雑さを加えることで、聴き手を飽きさせない工夫が凝らされています。バルーンさんの楽曲は、全体的に洗練されたコードワークが多く、分数コードが多用されている傾向にあります。
「Calc.」 (ジミーサムP feat. 初音ミク): この楽曲では、随所に分数コードが効果的に使用されており、曲全体の洗練された雰囲気や、切なくも美しい世界観を演出するのに貢献しています。特に、穏やかながらも感情が揺れ動くような部分で、ベースラインの動きと分数コードが相まって、深い響きを生み出しています。
4. 意外性でハッとさせる!ノンダイアトニックコードの活用
ノンダイアトニックコードとは、文字通り「ダイアトニック(そのキーに含まれる音)ではない」コードのこと。つまり、その曲のキー(調)に本来含まれていない音を使ったコードを指します。これらを効果的に使うと、聴き手に「おっ?」と思わせるような、意外性のあるコード進行を作り出し、楽曲に深みや奥行きを与えることができます。
例えば、明るい長調の曲中に突然短調のコードを挟むことで、一瞬の影を落とし、感情的なコントラストを生み出すことができます。ただし、使いすぎると耳障りになったり、調性が曖昧になったりすることもあるため、「ここぞ!」という時にピンポイントで使うのがポイントです。
具体的な使用例:
ノンダイアトニックコードの代表的な使い方をいくつかご紹介します。
- サブドミナントマイナーの借用: 長調の曲で、IVm(4度のマイナーコード)やIIm7-5(2度のマイナーセブンフラットファイブ)など、同じ主音を持つ短調からコードを借りてくる方法です。
例:Cメジャーキーの曲でC - G - Am - Fm(Fの代わりにFmを使用)F(ファラド)は明るい響きですが、Fm(ファラ♭ド)を使うと、急に切なさや憂鬱な雰囲気が生まれます。王道進行の途中に差し込むことで、聴き慣れた響きに新鮮な驚きと感情の揺らぎを与えることができます。これは、映画やアニメのBGMで、楽しい場面から急にシリアスな場面に切り替わるような演出にも似ています。 - セカンダリードミナント: 一時的に別のキーに転調したかのように聴かせるコードです。特定のコードへ解決する際に、そのコードのドミナントコード(V7)を借用します。
例:Cメジャーキーの曲で、Amに解決したい場合C - F - E7- Am(AmのV7であるE7を借用)このE7はCメジャーキーには含まれないコードですが、次に続くAmへの「解決感」を強め、聴き手に心地よい緊張感と解放感を与えます。楽曲の盛り上がりやサビの直前などに使うと、ドラマティックな演出が可能です。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
ノンダイアトニックコードは、ボカロ曲においても楽曲の個性を際立たせ、聴き手の記憶に残るメロディラインを生み出すために頻繁に用いられています。
「乙女解剖」 (DECO*27 feat. 初音ミク): DECO*27さんの楽曲は、一見ポップでありながら、コードワークが非常に凝っていることで知られています。この曲も例外ではなく、サビや間奏などで、キーから外れたコードが自然に、かつ効果的に挿入されています。これにより、楽曲全体に独特の浮遊感や、どこか影のある美しさが加わり、聴き手を惹きつけます。特に、感情の機微を表現する場面で、意図的に不協和音に近い響きを作り出すことで、楽曲の深みを増しています。
「ロキ」 (みきとP feat. 鏡音リン・初音ミク): この曲は非常にキャッチーでロックな楽曲ですが、随所にノンダイアトニックコードやそれに準ずるコードが効果的に使われています。特に、AメロやBメロからサビへの移行部分などで、聴き手をハッとさせるようなコードの変化が見られ、それが楽曲の疾走感と中毒性を高める要因の一つとなっています。突然の転調のような響きや、予想を裏切るコード展開が魅力です。
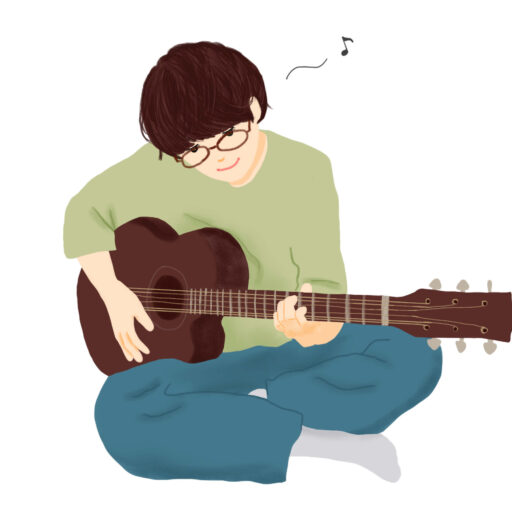
このテクニックは僕のおすすめです!!
5. 短調曲に光を!メジャーコードを効果的に使う方法
短調(マイナーキー)の曲は、一般的に暗く、切ない、悲しいといったイメージを持たれがちです。しかし、その中にメジャーコードを効果的に差し込むことで、希望の光が差し込むような、あるいは感情の揺れ動きを表現するような、ドラマティックな展開を生み出すことができます。このテクニックは、楽曲に奥行きと多様な感情をもたらし、聴き手の心を深く揺さぶります。
具体的な使用例:
短調の曲でメジャーコードを効果的に使う方法はいくつかあります。
- 同主長調への一時的な移行(ピカルディの三度): 短調の曲の終盤、特に最後のコードを同主長調(同じ主音を持つ長調)のI度メジャーコードに解決させる方法です。これを「ピカルディの三度(Picardy third)」と呼びます。
例:Am(イ短調)の曲で、通常ならAmで終わるところを...Dm - G - C(Amの同主長調CメジャーのI度コードで終わる)あるいは、曲の途中のカデンツ(終止形)で一時的に使用することも。...F - G - C(本来AmキーならAmで解決するところをCで解決)これにより、それまでの切ない雰囲気が一転、一筋の光が差し込むような、希望に満ちた、あるいは力強い印象を聴き手に与えます。バラードのエンディングや、感動的なシーンで非常に効果的です。 - ドミナントモーションにおけるメジャーコードの活用: 短調のドミナントコードは通常マイナーセブンス(例:AmキーならEm7)ですが、これをメジャーセブンス(E7)にすることで、長調と同じように**強い解決感(ドミナントモーション)**を生み出すことができます。
例:AmキーでAm - Dm - E7 - AmこのE7は、Amキーのハーモニックマイナースケール(和声的短音階)に由来するコードで、Amへの強い引力を持っています。これにより、単なる「暗さ」だけでなく、情熱的で力強い雰囲気を表現することが可能になります。特に、サビの頭や、楽曲の重要な展開部分で使うと、聴き手に強いインパクトを与えられます。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
短調の曲にメジャーコードを効果的に用いることで、楽曲に多様な感情表現と深いドラマ性を持たせているボカロ曲は数多く存在します。
「劣等上等」 (Giga feat. 鏡音リン・レン): この楽曲もマイナーキーが中心ですが、非常にパワフルでアグレッシブな印象を与えます。その理由の一つに、随所でドミナントコードに長三度が含まれるハーモニックマイナー由来のコードや、一時的な同主長調への転調のような響きが使われている点が挙げられます。これにより、切なさだけではない、力強さや高揚感が楽曲全体にみなぎり、聴き手を熱狂させるドライブ感を生み出しています。
「砂の惑星」 (ハチ feat. 初音ミク): この曲は全体的にマイナーキーが基調となっていますが、サビなどでメジャーコードへの一瞬の移行や、ドミナントモーションの解決にメジャー系の響きが使われている箇所があります。これにより、単なる暗さだけでなく、荒廃した世界の中にもかすかな希望や、力強さ、あるいは皮肉めいた明るさを感じさせる独特の世界観を作り出しています。特に、曲の進行の中で聴き手の感情を揺さぶるようなコードの変化に注目すると、メジャーコードの活用が楽曲に与える影響がよく分かります。
6. 疾走感と安定感!クリシェでドラマティックに
**クリシェ(Cliché)**とは、音楽理論では「常套句」や「決まり文句」といった意味合いを持ちますが、コード進行においては、特定のコードの構成音(特にベースラインや内声)が段階的に(半音または全音で)変化していくことで、聴き手に安定感と同時に推進力や疾走感を与えるテクニックを指します。特にベースラインが半音ずつ下降していくパターンが有名で、J-POPやアニソン、映画音楽など、感情を揺さぶる楽曲で非常によく使われています。サビに向かって盛り上げたい時や、物語の展開に合わせて感情を高めたい時に使うと、楽曲がよりドラマティックになります。
具体的な使用例:
クリシェには様々なパターンがありますが、ここでは代表的なものを2つご紹介します。
- 下降クリシェ(ベースラインが半音ずつ下降): 最も一般的で、切なさや叙情感、または壮大さを演出したい時に使われます。
例:C - G/B - Am - G#/Aこの例では、Cのコードから始まり、ベース音がC→B→A→G#と半音ずつ下降していきます。 これに加えて、C - G/B - Am - Am/G# - C/G - F#m7-5 - F - C/E - Dm7 - Gsus4 - G - Cのような形で、コードが変化していく中でベースラインが段階的に下降することで、聴き手に**「動き」と「次の展開への期待感」**を与えます。特にバラードのAメロやBメロで使うと、メロディに寄り添いながら感情の深まりを表現できます。 - 上行クリシェ(内声やトップノートが半音ずつ上行): こちらは、高揚感や希望、または不安感などを表現したい時に使われます。例:
Am - AmM7 - Am7 - Am6この進行では、AmコードのトップノートがA→A#→B→Cと半音ずつ上行していきます。ベース音はAで固定されたままで、コードの響きだけが変化します。 これにより、少しずつ状況が好転していくような、あるいはじわじわと何かが近づいてくるような緊張感を演出できます。楽曲のクライマックスに向かう部分や、謎めいた雰囲気を表現したい時にも効果的です。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
クリシェは、ボカロ曲においても楽曲の感情表現を豊かにし、リスナーの印象に残るメロディラインを際立たせるために多用されています。
「心拍数#0822」 (蝶々P feat. 初音ミク): 切ないバラード調の楽曲ですが、随所でクリシェ的なコード進行の動きが見られます。特に、ベースラインが段階的に下降していくパターンが効果的に使われており、それが歌詞の感情の揺れ動きや、切ない心情をより一層引き立てています。聴き手に「じんわりと心に染み渡る」ような感動を与える上で、クリシェのテクニックが重要な役割を果たしています。
「ハッピーシンセサイザ」 (EasyPop feat. GUMI・巡音ルカ): この楽曲は全体的に明るくポップな印象ですが、間奏やサビの一部などで、ベースラインのクリシェに近い動きが使われています。特に、流れるようなコード進行とベースラインの滑らかな動きが相まって、楽曲に心地よい疾走感と安定感を与え、中毒性を高めています。
7. 憧れのあの曲も!循環コードで無限ループ
ボカロ曲には、一度聴いたら頭から離れない、中毒性のある繰り返しが魅力的な曲がたくさんありますよね。その魅力を支えているのが、他でもない循環コードです。循環コードとは、同じコード進行を何度も繰り返すことで、楽曲に安定感と独特のリズム感を与え、聴き手を心地よいループの中に引き込むテクニックです。
ただ単に繰り返すだけでなく、少しずつアレンジを加えたり、メロディや伴奏のパターンを変えたりすることで、飽きさせない「無限ループ」を作り出すことができます。これは、楽曲に統一感をもたせつつ、徐々に盛り上がりを構築したり、違った表情を見せたりするのに非常に効果的です。
具体的な使用例:
循環コードは、特にAメロやBメロ、サビなど、楽曲の核となる部分で頻繁に使われます。
- シンプルで定番の循環コード: J-POPやボカロ曲で最もよく耳にする循環コードの一つが、いわゆる「王道進行」を繰り返すパターンです。
例:C - G - Am - Em - F - C - Dm7 - G(これを繰り返す)この進行は安定感があり、どんなメロディにも合わせやすいのが特徴です。繰り返すことで、聴き手に安心感と親しみやすさを与えます。 - 変化を加えた循環コード: 同じコード進行を繰り返す中でも、様々な工夫で飽きさせない工夫ができます。
- ベースラインのバリエーション: 毎回同じベースラインではなく、オクターブを変えたり、ウォーキングベースにしたりする。
- ボイシングの変化: コードの構成音の並び方を変えたり、テンションコードを加えたりして、響きに変化をつける。
- リズムパターンの変化: 伴奏のドラムやリズム隊のパターンを徐々に複雑にしたり、シンプルにしたりする。
- メロディの変化: 同じコード進行の上で、メロディラインを少しずつ変化させたり、別のパート(ハモリなど)を加えたりする。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
多くのボカロ曲が循環コードを効果的に使用しており、それが楽曲の中毒性や人気に繋がっています。
「DECORATOR」 (kz feat. 初音ミク): エレクトロニックなダンスミュージック色の強いこの楽曲も、特徴的な循環コードが繰り返し使われています。特に、その反復によって生まれるグルーヴ感と、様々なシンセサウンドのレイヤーが加わることで、楽曲全体に中毒性と多幸感をもたらしています。単なる繰り返しのようでいて、細部にわたるアレンジの変化が、聴き手を飽きさせない工夫となっています。
「千本桜」 (黒うさP feat. 初音ミク): この曲は、サビを中心に非常に印象的な循環コードが繰り返されています。そのコード進行の力強さと、疾走感あふれるメロディ、そして和風ロックなアレンジが相まって、聴き手に強烈なインパクトを与え、一世を風靡しました。同じコード進行が繰り返されることで生まれる一体感と高揚感が、楽曲の魅力を最大限に引き出しています。

初心者におすすめだにー!!
8. ジャジーな響きをプラス!テンションコードで彩る
「もっと大人っぽい雰囲気にしたい」「洗練されたサウンドにしたい」「ちょっと複雑でおしゃれな響きが欲しい」――そんな時にぜひ試してほしいのがテンションコードです。
テンションコードとは、通常のトライアド(三和音)やセブンスコードに、さらに特定の音(テンションノート)を付け加えたコードのこと。例えば、Cに9thの音を加えたCadd9(シーアドナインス)や、Cmaj7に9thの音を加えたCmaj7(9)(シーメジャーセブンナインス)などがあります。これらの音を加えることで、一気にジャジーでおしゃれな、奥行きのある響きが生まれ、ボカロ曲の表現の幅がグッと広がります。
具体的な使用例:
テンションコードは、特にコード進行の途中で彩りを加えたり、楽曲の雰囲気をガラッと変えたい時に効果的です。
- シンプルなコードをおしゃれに変化させる: 基本のコードにテンションを加えるだけで、まるで別物のような響きになります。
例:C - G - Am - F(王道進行) →Cmaj7(9) - G7(13) - Am7(11) - Fmaj7(#11)このように、それぞれのコードに適切なテンションを加えることで、**聴き慣れた王道進行が、一瞬にしてジャズバーのような大人っぽい雰囲気に変わります。**特に、スローテンポのボカロ曲や、R&B、シティポップのようなジャンルの楽曲に合わせると、非常に効果的です。 - 浮遊感や透明感を出す: 9thや11th、13thといったテンションノートは、コードに独特の響きと浮遊感を与えます。特に、浮遊感を強調したい場合は、コードの構成音から一部の音を省略してテンションノートを際立たせる「オープンボイシング」で弾くと良いでしょう。
例:Cadd9(C-E-G-D)やAm7(9)(A-C-E-G-B)など。これらのコードを、ゆったりとしたアルペジオで聴かせると、キラキラとした透明感や、夢の中にいるような幻想的な雰囲気を演出できます。ボカロのアンビエント曲や、切ないバラード、あるいは星空をテーマにした楽曲などにぴったりです。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
テンションコードは、ボカロPの中でも特にサウンドへのこだわりが強いクリエイターによって、楽曲のクオリティを上げるために多用されています。
「プロトディスコ」 (ぬゆり feat. flower): ぬゆりさんの楽曲は、独特の浮遊感と中毒性のあるサウンドが特徴で、テンションコードが頻繁に用いられています。この曲も、単なるポップなコード進行に留まらず、テンションを加えることで楽曲に予測不可能な展開や、都会的なクールさを与えています。特に、サビやブリッジでのコードの変化に注目すると、テンションコードがどのように楽曲の雰囲気を変えているかを感じ取れます。
「夜明けと蛍」 (n-buna feat. 初音ミク): n-bunaさんの楽曲は、繊細で叙情的な世界観が特徴ですが、そのサウンドを支えているのが巧みなテンションコードの活用です。この曲でも、コード進行の中に9thや11thといったテンションが自然に溶け込んでおり、楽曲全体に透明感と複雑な感情のニュアンスを与えています。特にピアノやギターの響きに耳を傾けると、テンションコードが織りなす美しいハーモニーを感じ取れるでしょう。
「Lemon」 (米津玄師): ボカロPとしても活動していた米津玄師さんの代表曲ですが、この楽曲はJ-POPでありながら、テンションコードが非常に効果的に使われています。特にサビや間奏などで、コードの響きに深みと哀愁を与え、聴き手の心を掴む要因の一つとなっています。ボカロ曲ではないですが、ボカロP出身の彼の楽曲は、テンションコードの使い方の参考になるでしょう。
9. 転調で広がる世界!ボカロ曲の展開力を上げる
曲の途中でキー(調)を変える**転調(Modulation)**は、楽曲に大きな変化と高揚感をもたらす、非常にドラマティックなテクニックです。AメロやBメロで築き上げた雰囲気を、サビでガラッと変えたり、間奏で全く別の世界観を表現したりと、ボカロ曲の展開力を飛躍的に高めることができます。
転調には、聴き手に強いインパクトを与える大胆な転調だけでなく、気づかないうちに自然にキーが変わっているような滑らかな転調もあり、あなたの楽曲に新たな息吹を吹き込んでくれます。
具体的な使用例:
転調には様々な方法がありますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。
- 半音上への転調(半音転調): 最も分かりやすく、聴き手に高揚感を与える転調方法です。サビの繰り返しや、曲のクライマックスで半音上に転調することで、一気に盛り上がりを演出できます。
例:Cメジャーキーの曲から、サビでD♭メジャーキーへ転調。
...G - C(Cメジャーで終わる) →D♭ - A♭ - B♭m - F♭(D♭メジャーのコード進行へ)この転調は、カラオケなどで「キーを上げる」のと同じ効果で、聴き手に「来た!」という感覚を与え、楽曲の盛り上がりを強調します。ボカロのアップテンポな曲や、熱いメッセージを伝えたい曲で非常に効果的です。 - 同主調への転調(マイナーからメジャー、またはその逆): 同じ主音を持つ長調と短調の間で転調する方法です。
例:Am(イ短調)の曲から、サビでAメジャーキーへ転調。
...Dm - E7 - Am(Amで終わる) →A - D - E - A(Aメジャーのコード進行へ)これにより、それまでの切ない雰囲気が一転、希望や力強さ、あるいは解放感を表現できます。感情の起伏を繊細に、かつ大胆に表現したい時に有効です。 - セカンダリードミナントを用いた転調(自然な転調): 特定のコードのドミナントコード(V7)を一時的に借用し、そこから自然に次のキーへ移行する方法です。聴き手は転調に気づかないうちに、いつの間にかキーが変わっているような印象を受けます。
例:Cメジャーキーの曲から、Fメジャーキーへ転調したい場合C - Dm - C7 - F(FのV7であるC7を挟んでFへ解決)このC7が、次のFメジャーキーへの橋渡しとなります。これにより、楽曲の流れを損なわずに、滑らかに雰囲気を変えることができます。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
転調は、ボカロ曲の構成に多様性をもたらし、聴き手の感情を深く揺さぶるために、多くの人気曲で用いられています。
「シャルル」 (バルーン feat. flower): この曲では、サビの繰り返しで半音転調が使われている箇所があり、楽曲にさらなるインパクトと高揚感を与えています。バルーンさんの楽曲は、コード進行が非常に洗練されており、転調も自然かつ効果的に行われることで、楽曲の深みが増しています。
「脳漿炸裂ガール」 (れるりり feat. 初音ミク・GUMI): この曲は、目まぐるしい展開と疾走感が特徴ですが、サビで半音上への転調が頻繁に用いられています。これにより、楽曲のテンションがさらに高まり、聴き手に強烈な高揚感と中毒性をもたらしています。転調が楽曲の勢いを加速させる典型的な例と言えるでしょう。
「千本桜」 (黒うさP feat. 初音ミク): この楽曲も、サビの繰り返しなどで半音上への転調が効果的に使われています。曲のクライマックスに向けてキーが上がっていくことで、聴き手の感情を煽り、楽曲全体のスケール感を大きくしています。和風ロックというジャンルの中で、転調が楽曲のドラマ性を高める重要な要素となっています。
10. コード進行に「ひねり」を加える!意外なコード展開
これまで、おしゃれなコード進行の具体的なテクニックをたくさん学んできましたね。王道進行の彩り方から、分数コード、テンションコード、そして転調まで。これらの知識を十分に理解したら、いよいよ最終ステップです。それは、あえてセオリーから外れた、予想外のコード進行を試してみることです。
これは「なんでもアリ」というわけではありません。やみくもに突拍子もないコードを並べるのではなく、聴き手に「おや?」と思わせつつも、どこか心地よく響くような、絶妙なバランスを見つけることが大切です。一般的な音楽理論の枠を超えたコード進行は、あなたのオリジナリティが光る、唯一無二のボカロ曲を生み出すための「最終兵器」になるはずです。
具体的な使用例:
「セオリーから外れる」とは、例えば以下のようなアプローチです。
- ノンダイアトニックコードの連続使用や予期せぬ解決: 通常は一瞬だけ挟むノンダイアトニックコードを連続させてみたり、本来解決すべきコードとは全く異なるコードへ解決させてみたりします。
例:CメジャーキーでC - F - G(ここまでは定番) →C - F - A♭maj7 - D♭maj7 - Gmaj7 - Cこの例では、Gの後に全く関係性のないA♭maj7やD♭maj7を挟み、さらにGmaj7(本来G7が多い)を経由してCに戻っています。これにより、聴き手に「次に何が来るんだろう?」という驚きと、ミステリアスな、あるいは幻想的な感覚を与えられます。特に、楽曲の中で夢や現実の境界線が曖昧になるような場面や、サイケデリックな雰囲気を表現したい時に効果的です。 - 不協和音の意図的な活用と不完全な解決: あえて濁った響きの不協和音(ディミニッシュコードやオーギュメントコードなど)を、一般的な使い方とは異なる文脈で多用したり、解決感を曖昧にしたまま次のセクションに進んだりします。
例:Am - G#dim - Adim - Bdim - Cこのように、ディミニッシュコードを連続させることで、不安定でスリリングな印象を与えます。ホラーやサスペンスのような緊張感を演出したい時や、心の葛藤を表現したい時に有効です。ただし、聴きやすいかどうかは紙一重なので、全体のバランスを考慮しましょう。 - 特定の音を軸にした自由なコード展開: 特定のメロディ音やベース音を固定し、その上に乗せるコードを、あえてキーにとらわれずに自由に選択していく方法です。
例:メロディが「ド」の音で停滞している間に、C - F#m7-5 - Bbm7 - Ebm7など、全く関係のないコードを次々試す。これにより、予測不能で実験的なサウンドが生まれます。聴き慣れない響きの中にも、軸となる音が聴こえることで、不思議な魅力やオリジナリティが生まれます。
このテクニックが使われているボカロ曲の例:
ボカロ曲の世界では、既存の枠にとらわれない自由な発想が尊重されるため、このような「ひねり」のあるコード進行は多くのクリエイターによって試みられています。
「ウミユリ海底譚」 (n-buna feat. 初音ミク): n-bunaさんの楽曲は、その幻想的な世界観を、緻密かつ自由なコードワークで表現しています。この曲では、通常のコード進行ではあまり見られない、複雑で予測不能な和音が連続したり、解決しないまま次のセクションに進んだりする箇所があります。これにより、海の中にいるような浮遊感や、夢のような非現実感、そして切なさが非常に深く表現されています。聴くたびに新たな発見があるような、奥行きのあるサウンドです。
「アンノウン・マザーグース」 (wowaka feat. 初音ミク): wowakaさんの楽曲は、一見シンプルに聴こえるようでいて、そのコード進行やベースラインには独特の癖や予測不能な動きが含まれていることが多いです。特に、特定のコードに対する一般的な解決をあえて避けたり、ノンダイアトニックな響きを連続させたりすることで、楽曲全体に狂気的な高揚感と、他にはないオリジナリティを生み出しています。彼の楽曲に耳を傾けると、セオリーの外側にある「カッコよさ」を見つけられるでしょう。
「ドラマツルギー」 (Eve): ボカロP出身のEveさんの楽曲は、キャッチーさの中に洗練されたコードワークと意外性が散りばめられています。この曲も、Aメロからサビにかけてのコード進行で、一般的なセオリーにはないコードを挟んだり、コードの響かせ方自体に「ひねり」を加えたりしています。これにより、楽曲全体に独特の浮遊感と、聴き手を飽きさせない中毒性が生まれています。特に、「このコードの次にこれ?」と思わせるような不意打ち感が魅力です。
DTM作曲を手早く上達させたいならシアーミュージック

- 迅速で自由な予約システム
ウェブサイトや電話を通じて、レッスンの日程、時間、場所を自由に選んで簡単にご予約いただけます。 - 相性の良い講師の選択
学びたい内容やコースに合わせて、最適な講師を自由にお選びいただくことが可能です。 - ストレスフリーを保証する教室環境
当社の教室は、充実したレッスンが受けられるリラックスした雰囲気を保証しております。 - 特別講師:登録者200万人を誇るYouTuber「しらスタ」
特別講師として、登録者200万人を超えるYouTuber「しらスタ」が在籍しております。
シアーミュージックは、自由に楽しく上達したい大人の初心者に最適な音楽教室です。
この教室は、大人の初心者が失敗を恐れずに安心して音楽を楽しめるように運営しております。
- 講師との相性が合わない
- レッスンスケジュールを守るのが難しい
これらの問題を解決するため、シアーミュージックでは学びたい内容やジャンルに応じて、講師を固定せずに自由に選べるレッスンを提供しています。
まるで大学の講義を選ぶような感覚で、自分に合った講師を選ぶことができ、忙しい大人の方に配慮し、レッスンスケジュールも自分でカスタマイズ可能です。
更に、オンラインレッスンもあるので、固定されたスケジュールがプレッシャーになることを避け、より柔軟にレッスンを受けられます。

時間管理がしやすいのは、忙しい人にとってはありがたいね!
シアーミュージックは、コストパフォーマンスが高いく、迅速で自由な予約システムを通じて、各地域の分布バランスによる通いやすさと利便性を提供し、リラックスした教室環境で継続的にレッスンを受けることができます。
また、口コミと評価の高い講師陣から、学びたい内容に最適な講師を選ぶことができるため、上達を確実にサポート、質の高い指導を受けることができます。
| シアーミュージック概要 | |
|---|---|
| 運営 | シアー株式会社 |
| 対応楽器 | ・バイオリン・ピアノ・エレキギター・アコースティックギター ・ベース・ウクレレ・ドラム・サックス・DTM |
| レッスン料 | ・月2回 / ¥10,000(税込¥11,000)※1レッスン当たり税込5,500円 ・月3回 / ¥13,500(税込¥14,850)※1レッスン当たり税込4,950円 ・月4回 / ¥16,000(税込¥17,600)※1レッスン当たり税込4,400円【一番お得】 |
| レッスン時間 | 1コマ45分 ※入替/準備の時間含む |
| レッスン形態 | マンツーマンレッスン |
| レベル | 趣味嗜好の方からプロ志向の方まで |
| 入会金 | 2,000円(税込2,200円) |
| 校舎 | ・北海道・青森・秋田・盛岡・仙台 ・新潟・郡山・金沢・長野・東京都内・東京近郊 ・岐阜・静岡・愛知・大阪・兵庫・岡山・倉敷・福山 ・広島・松山・博多・小倉・福岡天神 ・熊本・鹿児島・那覇 ・オンライン |
| 無料特典 | ・練習室を無料でレンタル可能 ・楽器レンタル無料 ・無料体験教室 |
| 公式サイト | シアーミュージック |
\「シアーミュージック」を無料で体験してみる!/
まとめ:あなたのボカロ曲が劇的に変わる!
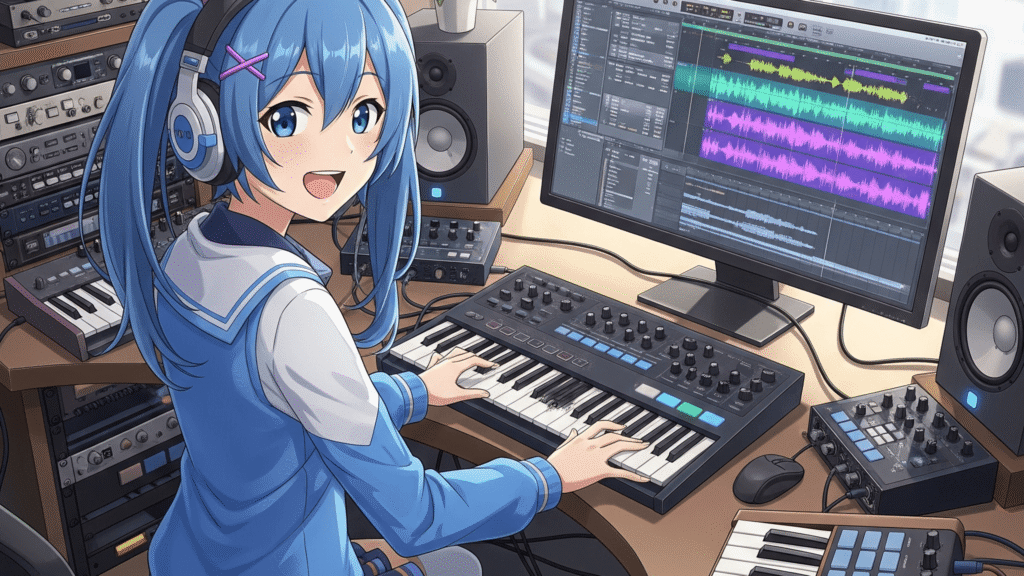
ここまで読んでくださり、ありがとうございます!
ボカロ曲を「もっとおしゃれにしたい」「聴く人の心に響かせたい」というあなたの情熱は、この記事でご紹介した様々なコード進行のテクニックで、きっと大きく花開くことでしょう。
最初は難しく感じるかもしれませんが、大切なのは、まず「やってみる」こと。この記事で解説した10種類のコード進行を、あなたの好きなボカロ曲のコード譜と照らし合わせてみたり、実際にDAWで打ち込んで音を聴いてみたりしてください。一つひとつのコードが持つ「色」や、進行が織りなす「感情」が、きっと見えてくるはずです。
そして、最終的には「セオリーを理解した上で、あえて崩してみる」という、あなただけのオリジナリティを追求してみてください。音楽に決まった正解はありません。あなたの感性で、自由に音を紡いでみましょう。
さあ、今日からあなたのボカロ曲を劇的に変える旅に出かけましょう!あなたの音楽が、より多くの人々に届くことを心から願っています。
新たなコード進行で、あなたのボカロ曲にどんな魔法をかけますか?ぜひ、挑戦してみてくださいね!