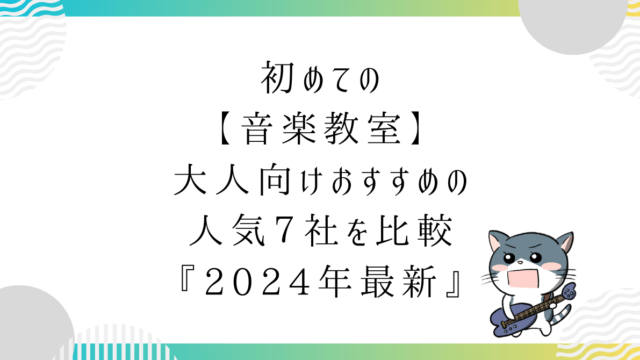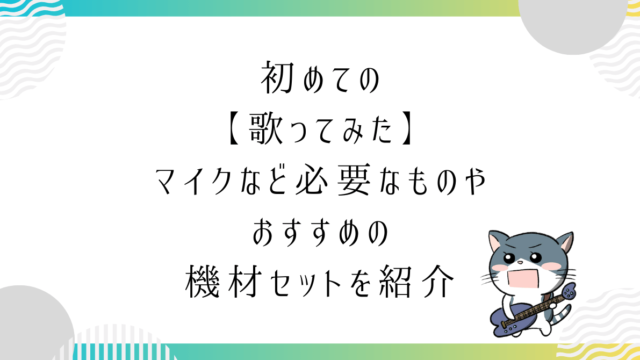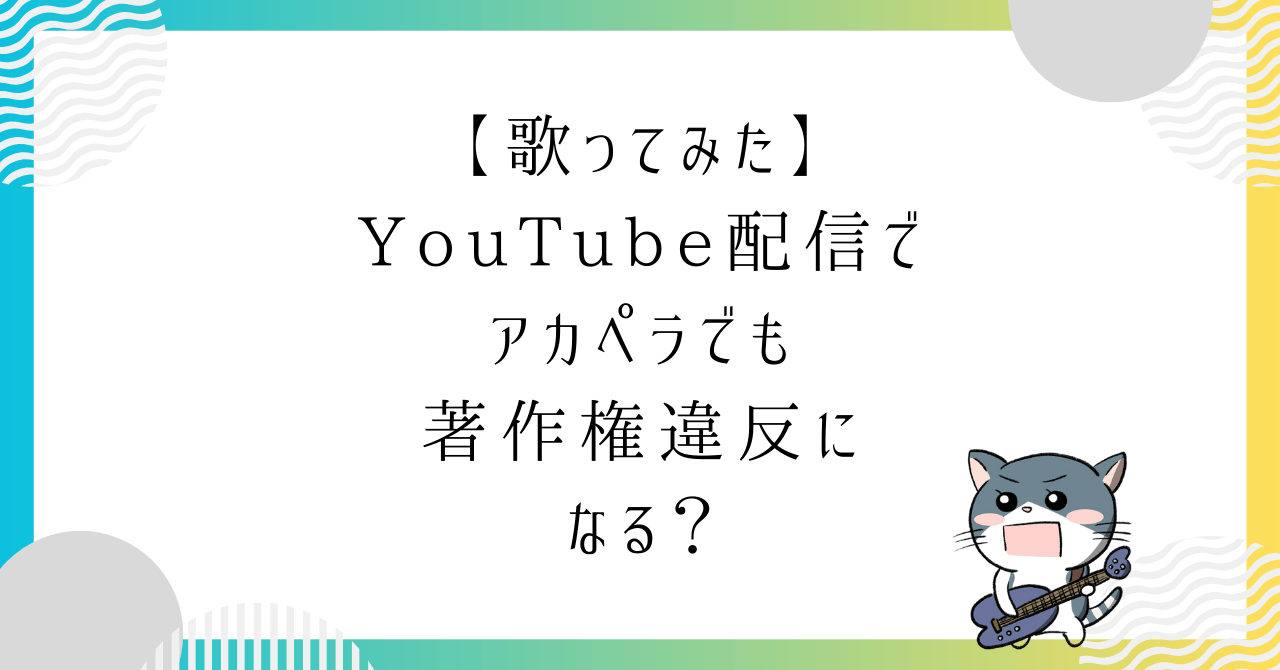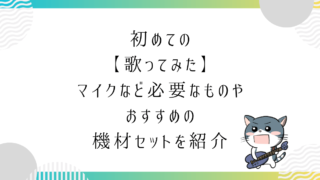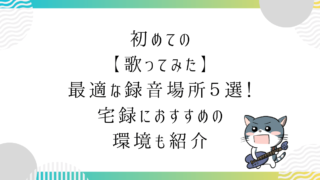YouTubeで「歌ってみた」を始めたいけど、アカペラなら著作権は大丈夫?そう考えたことはありませんか?カラオケ音源を使わなければ問題ないと思いがちですが、実はそこに大きな落とし穴があります。この疑問に結論からお答えします。

この記事では、アカペラ配信でも著作権侵害になる理由を、著作権と著作隣接権の違いから分かりやすく解説するよ!
さらに、安心して活動を続けるための具体的な方法まで、すべてお教えします。著作権の知識をしっかり身につけて、あなたの歌声を世界に届けましょう!
結論|アカペラでも著作権侵害になる可能性はある?

結論から言うと、アカペラで歌うだけでも著作権侵害になる可能性は十分にあります。 多くの人が「カラオケ音源を使わなければ大丈夫」と考えがちですが、著作権法はメロディ(曲)と歌詞自体を保護の対象としています。そのため、たとえ自分の声だけで歌ったとしても、元の曲や歌詞をそのまま使えば、著作権者の許諾が必要です。
1.1 「歌ってみた」は著作権の何にあたる?
「歌ってみた」という行為は、著作権法の観点から複数の権利に該当します。具体的には以下の通りです。
| 著作権 | 該当する行為 | 概要 |
| 演奏権 | 歌う、演奏する | 著作物を公衆に聞かせる権利です。アカペラでも、歌を公衆に配信する時点でこの権利が関係します。 |
| 公衆送信権 | YouTubeにアップロードする | 著作物をインターネットを通じて公衆に送信する権利です。動画を配信する行為そのものがこれに該当します。 |
| 複製権 | 録音・録画する | 著作物をコピーする権利です。歌っている姿を録画したり、音声を録音したりする行為がこれにあたります。 |
| 公衆伝達権 | 配信されたものを聞かせる | 放送されたものを公衆に聞かせる権利です。YouTube Liveなどで歌っているものを画面共有などで見せる場合に該当します。 |
これらの権利は、すべて著作権者が独占的に持っているため、無断で使用することは原則として認められていません。
1.2 著作権には「著作権」と「著作隣接権」の2種類がある
著作権は大きく分けて「著作権」と「著作隣接権」の2つがあります。この違いを理解することが、「歌ってみた」を安全に行うための第一歩です。
- 著作権(著作財産権): 作詞家や作曲家が持つ権利です。歌詞やメロディそのものを保護する権利で、この許諾なく歌うことはできません。
- 著作隣接権: 実演家(歌手など)、レコード制作者(レコード会社など)、放送事業者などが持つ権利です。他人の曲を歌う場合、カラオケ音源やMVなど、原盤を使用する際にこの権利が関係します。アカペラの場合は基本的には問題になりませんが、音源の一部や、元のアーティストの歌唱スタイルを真似るなど、その実演を彷彿とさせるような場合には注意が必要です。
2. 【曲と歌詞】著作権の権利とアカペラで違反になるケース

アカペラであっても、歌詞やメロディを歌うだけで、許諾なく配信すれば著作権侵害になります。
たとえ自分の声だけで歌ったとしても、その歌詞とメロディは作詞家や作曲家が創作した「著作物」です。そのため、著作権者の許可を得ずに公衆に公開することは、著作権(公衆送信権や演奏権など)の侵害に該当します。これは、著作権法で明確に定められています。
具体例:
- Aさんのオリジナル曲を、許可なくYouTubeでアカペラで歌って配信
- Bさんの人気曲の替え歌を、原曲のメロディを使ってアカペラで披露
- Cさんの曲をアカペラで歌うだけでなく、自分でアレンジを加えたバージョンを配信
これらの行為はすべて著作権者の権利を侵害している可能性が高く、最悪の場合、損害賠償請求や刑事罰の対象となりえます。
2.1 著作権を管理する団体(JASRAC・NexTone)とは?
日本の多くの楽曲の著作権は、JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexTone(ネクストーン)といった著作権管理団体がまとめて管理しています。これらの団体は、作詞家や作曲家から著作権の管理を委託され、利用者が円滑に楽曲を使えるようにしています。
YouTubeのようなプラットフォームは、これらの管理団体と包括的な利用許諾契約を結んでいます。これにより、ユーザーがこれらの管理団体が管理している楽曲を使用する場合、原則として個別に許諾を得る必要がなくなります。
2.2 JASRACと包括契約しているYouTubeなら大丈夫?
結論、JASRACと包括契約しているYouTubeであっても、すべての曲が「歌い放題」というわけではありません。
YouTubeはJASRACやNexToneと包括契約を結んでいるため、原則としてこれらの団体が管理している楽曲を歌う(演奏権)ことや、歌詞を表示すること(公衆送信権)は、著作権侵害になりません。しかし、例外や注意すべき点が存在します。
【注意点】
- 管理外の楽曲: 著作権者が管理団体に管理を委託していない楽曲(例:インディーズアーティストの楽曲、海外の特定の楽曲など)は、包括契約の対象外です。これらの楽曲を歌う場合は、個別に著作権者へ許諾を得る必要があります。
- 海外の楽曲: 海外の楽曲もJASRACが管理しているケースが多いですが、一部の楽曲は管理外です。また、著作権の国際的な扱いは複雑なため、トラブルになるリスクがあります。
- 利用方法の制限: YouTubeの包括契約は、あくまで「歌ってみた」のような利用方法に限られます。商用利用や、楽曲を改変して利用する(替え歌など)場合は、別途許諾が必要になることがあります。
3. 【著作隣接権】アカペラで歌う際に注意すべき権利

アカペラで歌う場合、カラオケ音源や公式MVを使わなければ、基本的には著作隣接権の侵害にはなりません。
しかし、著作隣接権は、実演家(歌手)やレコード制作者(レコード会社)が持つ権利です。アカペラであっても、その実演や音源の扱いに少しでも関わる場合は注意が必要です。
3.1 誰が「著作隣接権」を持っている?
著作隣接権は、以下の3者が持っています。
- 実演家: 歌手や演奏者など、楽曲を実際に歌ったり演奏したりする人です。
- レコード制作者: レコードやCD、ストリーミング音源などを制作・提供するレコード会社などです。
- 放送事業者: テレビ局やラジオ局などです。
例えば、人気アーティストの楽曲をYouTubeでアカペラで歌う場合、その歌唱スタイルを過度に模倣したり、ライブ映像の一部を切り取って使用したりすると、実演家やレコード制作者の権利(著作隣接権)を侵害する可能性があります。
3.2 YouTubeの著作隣接権の扱いはどうなってる?
YouTubeは、著作隣接権についても多くのレコード会社と包括契約を結んでいます。
これにより、ユーザーは著作権だけでなく、原盤(カラオケ音源や公式のバックトラックなど)を使用する場合も、基本的には個別に許諾を得る必要がありません。YouTubeに動画をアップロードすると自動的にContent IDという仕組みで著作隣接権を検知し、権利者に収益を分配したり、広告を表示したりするシステムが働きます。
しかし、これも包括契約を結んでいないレコード会社の楽曲や、YouTubeのシステムが検知できないような特殊なケースでは、別途許諾が必要になる場合があります。
4. アカペラ配信で著作権侵害にならないための対策

アカペラ配信で著作権侵害のリスクをゼロにするための、具体的な対策を3つご紹介します。
4.1 著作権フリー・パブリックドメインの楽曲を利用する
最も安全な方法は、著作権フリーの楽曲や、著作権が消滅した「パブリックドメイン」の楽曲を利用することです。
- 著作権フリー: 著作権者が無料で利用を許可している楽曲です。配布サイトからダウンロードして利用できます。
- パブリックドメイン: 著作権の保護期間が終了した楽曲です。日本では、原則として作者の死後70年を経過した楽曲がこれに該当します。例として、クラシック音楽や童謡の一部などが挙げられます。
これらの楽曲は、事前の許諾なく自由に利用できますが、利用規約や条件が設定されている場合もあるため、利用前に必ず確認することが重要です。
4.2 著作権者・著作隣接権者から直接許可を得る
YouTubeの包括契約対象外の楽曲を利用したい場合は、著作権者(作詞家・作曲家)や著作隣接権者(レコード会社など)に直接連絡を取り、許諾を得る必要があります。
メールや問い合わせフォームを通じて、「楽曲名」「利用目的(YouTubeでのアカペラ配信)」「チャンネルURL」などを明確に伝え、許諾をもらいましょう。この際、口頭ではなく、書面やメールなど形に残る形で許諾を得ておくことが大切です。
4.3 自分のオリジナル曲を歌う
最もシンプルで安全な方法は、自分で作詞・作曲したオリジナル曲を歌うことです。自分の作品であれば、著作権は自分自身に帰属するため、誰の許可も必要ありません。クリエイターとしての活動を広げる意味でも、オリジナル曲は非常に有効な手段です。
2026最新Q&A:『歌ってみた』著作権の疑問を解消

「歌ってみた」活動を安全に、そして長く続けるためには、正しい著作権知識が欠かせません。2026年現在の最新ルールに基づき、初心者が迷いやすいポイントをQ&A形式で解説します。
Q1. アカペラや弾き語りで歌うだけでも著作権侵害になりますか?
A. はい、無断で配信すれば侵害に該当する可能性があります。 「伴奏(音源)を使わなければ大丈夫」と誤解されがちですが、歌詞やメロディ自体が著作物として保護されています。ただし、YouTubeやニコニコ動画などのプラットフォームはJASRAC等と「包括契約」を結んでいるため、管理楽曲であれば自分で演奏したり歌ったりする分には、個人で許諾を得る必要はありません。
Q2. JASRAC管理曲なら、CDの音源やカラオケ店の音源をそのまま使っていい?
A. いいえ、それは「隣接権(原盤権)」の侵害になります。 JASRACとの包括契約は「楽曲(メロディや歌詞)」の使用を許可するものですが、CD音源やカラオケ音源には「原盤権(レコード製作者の権利)」が別に存在します。これらを動画に使うには、レコード会社やカラオケ会社から個別の許可を得る必要があります。基本的には、「自分で作った伴奏」や「二次利用が許可されたインスト音源」を使用しましょう。
Q3. 「替え歌」や「アレンジ」なら著作権に引っかかりませんか?
A. 原曲の同一性を損なうアレンジは、別途「著作者人格権」への配慮が必要です。 歌詞を勝手に変える「替え歌」や、原曲のイメージを大きく損なうような改変は、著作者が持つ「同一性保持権」に触れる可能性があります。特に商用利用や大規模な活動を検討している場合は、事前に権利者の意向を確認するのが安全です。
Q4. JASRACやNexToneの管理曲かどうか、どうやって調べればいい?
A. 各団体の公式データベースで検索可能です。 2026年現在も、以下のデータベースで作品名やアーティスト名から検索できます。
- J-WID(JASRAC)
- NexTone 作品検索 ここで「配信」の項目に「◯」がついていれば、包括契約済みのプラットフォーム(YouTube等)で歌うことが可能です。
Q5. 著作権フリーの曲なら、どんな使い方をしてもOK?
A. サイトごとの「利用規約」を必ず守りましょう。 「著作権フリー=何でも自由」という意味ではありません。「クレジット表記が必要」「営利目的はNG」「アダルトコンテンツでの使用禁止」など、サイトごとにルールがあります。代表的なサイトであるDOVA-SYNDROMEなどを使用する際は、必ず最新の規約に目を通す習慣をつけましょう。
まとめ|アカペラでも慎重に!著作権を理解して「歌ってみた」を楽しもう
「歌ってみた」は、アカペラであっても著作権侵害になる可能性があります。
YouTubeの包括契約があるからといって安易に考えるのではなく、著作権(曲と歌詞)と著作隣接権(実演や音源)という2つの権利を正しく理解し、慎重に対応することが重要です。
今回ご紹介した「著作権フリー・パブリックドメインの楽曲を利用する」「直接許諾を得る」といった対策を講じれば、安心して「歌ってみた」活動を続けることができます。著作権はクリエイターを守るための大切な法律です。ルールを守って、安全にクリエイティブな活動を楽しみましょう。