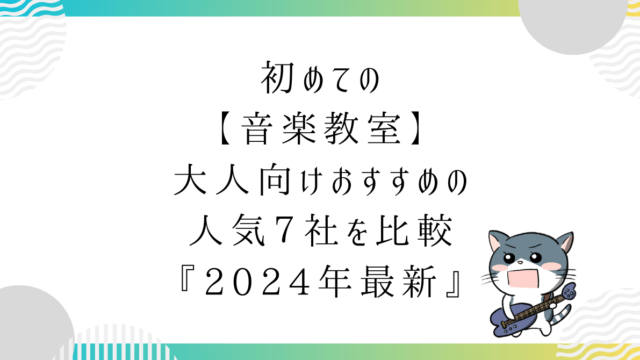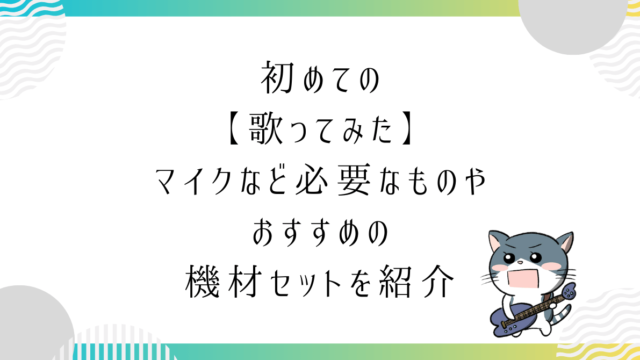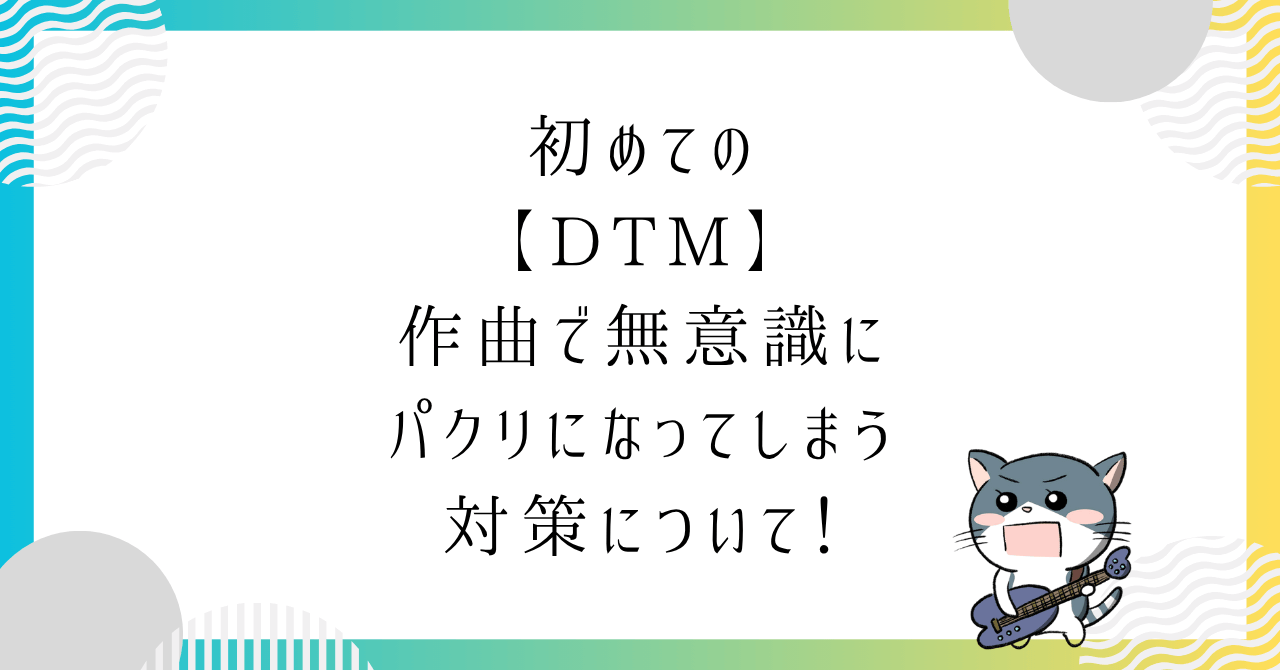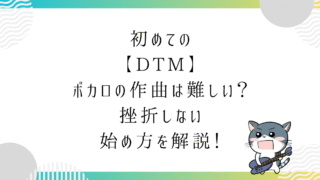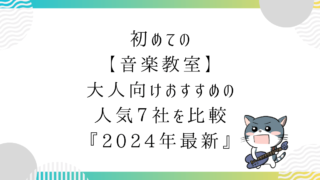「DTMで初めて作曲してみたけれど、なんだかどこかで聴いたことのある曲に似てしまう……。」そんな経験はありませんか?せっかく時間と情熱を注いで作ったオリジナル曲が、無意識のうちに「パクリ」になってしまうのは、DTM初心者さんにとってよくある悩みの一つです。
「もしかして、私の曲ってオリジナルじゃない?」そんな不安を感じる必要はありません。実はこれ、多くの作曲家が通る道なんです。

この記事では、DTM初心者さんが陥りがちな「無意識のパクリ」を回避し、真に独創的な楽曲を生み出すための具体的な対策を徹底解説するよー!
さらに、DTMスクールの活用が、この悩みを解決し、あなたの作曲スキルを飛躍的に向上させる強力な手段となる理由にも触れていきます。あなたの閃きを最大限に活かし、心から納得できる「自分だけの音」を見つけるヒントが満載です。さあ、自信を持って作曲を楽しむための第一歩を踏み出しましょう!
\DTMの情報が沢山!上達も早くなる!/
【DTM】作曲初心者が「無意識にパクリ」になってしまうのはなぜ?
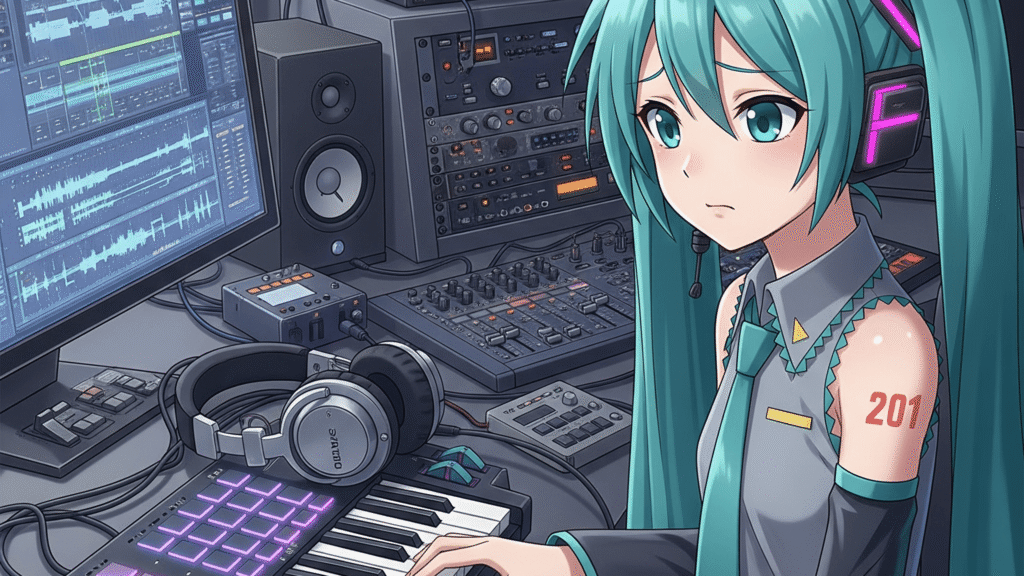
DTMで作曲を始めたばかりの頃、「あれ?このメロディ、どこかで聴いたことあるな……」と感じた経験はありませんか?一生懸命作ったはずのオリジナル曲が、知らず知らずのうちに既存の曲に似てしまう、「無意識のパクリ」は、多くの作曲初心者が直面する共通の悩みです。
なぜ、こうした現象が起きてしまうのでしょうか?その主な理由を掘り下げていきましょう。
耳コピや既存曲からの影響が強すぎるケース
作曲を学ぶ上で、好きな曲を聴き込んだり、耳コピをして分析したりすることは非常に有効な学習方法です。しかし、これが「無意識のパクリ」に繋がる大きな要因となることがあります。
私たちは普段から膨大な量の音楽を耳にしており、その中で特に印象に残ったフレーズやコード進行は、無意識のうちに脳にインプットされています。いざ自分で作曲しようとしたとき、引き出しの少ない初心者の段階では、この無意識のインプットが、あたかも自分のアイデアであるかのように表に出てきてしまうのです。
例えば、
- 好きなアーティストの曲ばかり聴いていると、そのアーティスト特有のメロディラインやリズムパターンが自然と自分の曲にも現れやすくなります。
- 特定のジャンルの音楽しか聴かない場合も、そのジャンルで頻繁に使われるコード進行やアレンジ手法を無意識のうちに模倣してしまうことがあります。
- 耳コピで楽曲構造を分析する際に、構成や展開までをそのままトレースしてしまうと、結果的に既存曲の「骨格」が残ってしまいやすくなります。
このように、音楽を深く吸収しようとする行為が、同時に「既存の枠組み」に囚われてしまうという、皮肉な現象が起こりやすいのです。
「オリジナリティ」への認識不足が招く問題
「無意識のパクリ」が起こるもう一つの要因は、「オリジナリティ」に対する認識の曖昧さにあります。特に作曲初心者の場合、「オリジナルな曲とは何か」という明確な基準がまだ確立されていないことが多いです。
- 「自分らしさ」の定義が不明確: 自分の個性や音楽的な嗜好がまだはっきりしていない段階では、「自分だけの音」をどう表現すれば良いか分かりません。そのため、既存の「良い」と感じるものを無意識に参考にしてしまいがちです。
- インプットの少なさ: 聴く音楽のジャンルが偏っていたり、分析する楽曲数が少なかったりすると、アイデアの引き出しが限られます。結果として、少ないインプットの中からしか組み合わせができず、結果的に誰かの曲に似てしまうことがあります。
- 盗作との混同: 「パクリ」と聞くと、意図的な盗作をイメージしがちですが、「無意識のパクリ」は悪意があるものではありません。しかし、その違いが明確に理解されていないと、似てしまうことへの対策が立てにくくなります。どこまでが「影響」で、どこからが「模倣」なのか、その線引きが難しいと感じることもあります。
作曲は、インプット(音楽を聴く・学ぶ)とアウトプット(実際に作る)のバランスが非常に重要です。インプットが多すぎたり、偏っていたりすると、アウトプットの際にそれが色濃く反映されてしまうのは自然なことなのです。大切なのは、この現象を理解し、適切な対策を講じることで、真のオリジナル楽曲へと繋げていくことです。
「パクリ」と「オマージュ」「インスパイア」の違いを理解する
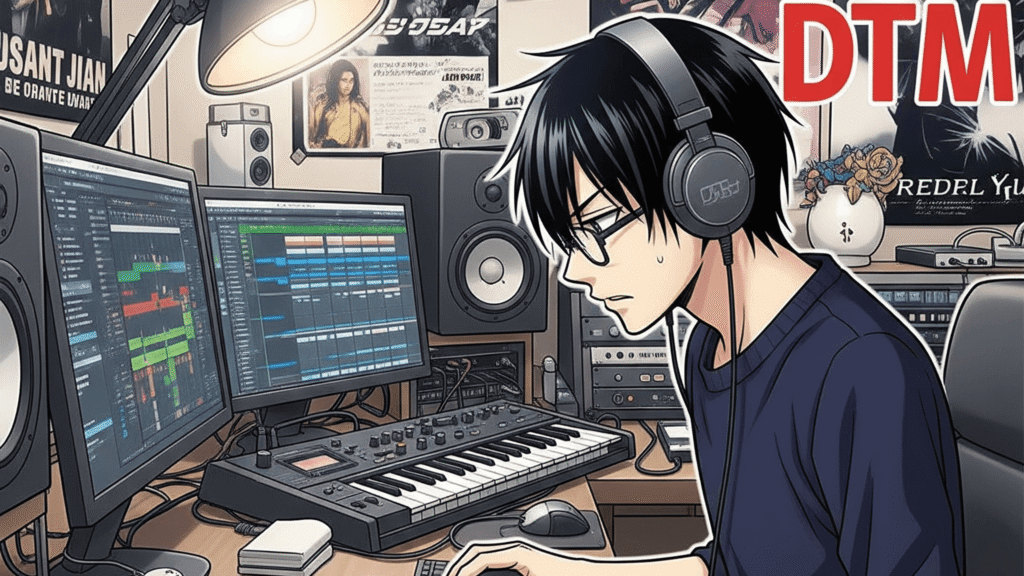
DTMで作曲をする上で、常に頭をよぎるのが「これって、どこかで聴いた曲に似てないかな?」という不安ですよね。特に「パクリ」という言葉は避けたいもの。では、一体どこからが「パクリ」で、どこまでが「オマージュ」や「インスパイア」として許容されるのでしょうか?この違いを理解することは、安心して作曲活動を続けるために非常に重要です。
どこからが「パクリ」になるのか?著作権の基本
音楽における「パクリ」とは、一般的に他者の楽曲の著作権を侵害する行為を指します。著作権とは、楽曲(メロディ、歌詞、コード進行、リズム、構成など)を作った人に自動的に与えられる権利のことです。これらは「著作物」として保護されています。
法的な観点から「パクリ」と判断される主な基準は、以下の2点です。
- 依拠性(いきょせい):他者の楽曲を知っていて、それを真似して作ったかどうか。つまり、「無意識」ではなく「意識的に」参照したかどうか、という側面です。
- 類似性(るいじせい):他者の楽曲と、表現形式が本質的に似ているかどうか。メロディの大部分が一致する、特徴的なコード進行やリズムパターンがそっくり、曲の構成や展開が酷似している、などが挙げられます。
この2つが揃った場合、「著作権侵害」、つまり「パクリ」と認定される可能性が高まります。特に、メロディの大部分や特徴的なフレーズが一致する場合は、盗作と見なされやすい傾向にあります。数小節程度の偶然の一致や、ありふれたコード進行の組み合わせだけで直ちにパクリとなるわけではありませんが、その判断は非常に難しいのが実情です。
合法的な「似た曲」を作るための境界線
では、既存の曲から影響を受けつつも、「パクリ」にならずにオリジナル曲を作るにはどうすれば良いのでしょうか?ここで、「オマージュ」や「インスパイア」という概念が重要になります。
- インスパイア(Inspired by…): これは「~に触発された、影響を受けた」という意味合いが強く、最も広い範囲で使われます。特定の曲やアーティストからアイデアや雰囲気を借りて、自分なりの解釈で全く新しいものを作り出す行為です。例えば、「この映画の雰囲気にインスパイアされた楽曲」のように、直接的なフレーズの引用はなく、あくまで「着想を得た」というレベルです。法的な問題はほとんどありません。
- オマージュ(Hommage): これは「尊敬する相手への敬意を示すための引用や模倣」を意味します。元ネタが誰の作品であるかを明確にし、意図的に特定のフレーズやサウンド、構成などを引用・再現しつつも、全体としてオリジナル作品としての価値を持つものを指します。例えば、ある有名曲のギターリフを短く引用して、それが元ネタへの「遊び心」や「リスペクト」として伝わるようなケースです。ただし、この「オマージュ」は非常にデリケートな境界線上にあり、受け取り手やその引用の程度によっては「パクリ」と見なされるリスクもゼロではありません。元ネタを「知っていなければ成立しない」という性質を持つため、リスナーが元ネタを知っている前提で楽しむような作品で使われることが多いです。
合法的な「似た曲」を作るための境界線は、**「引用の程度」と「オリジナル要素の比重」**にあります。
- 短すぎる、あるいは普遍的なフレーズは問題になりにくい:童謡のような誰でも思いつくような単純なメロディや、ごく短いリズムパターンなどは、著作権侵害を問われることは稀です。
- アレンジや再構築の徹底:既存の曲からインスピレーションを得たとしても、その要素を分解し、全く異なるリズム、コード進行、楽器編成、曲の構成などで再構築することで、オリジナリティを高めることができます。
- 意図しない類似への意識:作曲中に「あれ?似てるかも?」と感じたら、一旦そのフレーズを寝かせてみたり、意図的に違う方向に展開させたりする意識が大切です。
- 多様なインプット:特定のジャンルやアーティストだけでなく、幅広い音楽を聴き、分析することで、引き出しが増え、無意識の模倣を避けやすくなります。
つまり、「パクリ」は意図せずとも著作権を侵害する可能性のある行為、「インスパイア」は着想を得るに留まる健全な創作活動、「オマージュ」は尊敬の念を込めた意図的な引用ですが、そのバランスが非常に重要になる、ということを覚えておきましょう。安心してDTMを楽しむためには、この違いを理解し、自分の作品に責任を持つ意識が不可欠です。
\DTMの情報が沢山!上達も早くなる!/
オリジナル性を高めるためのインプット・アウトプット術
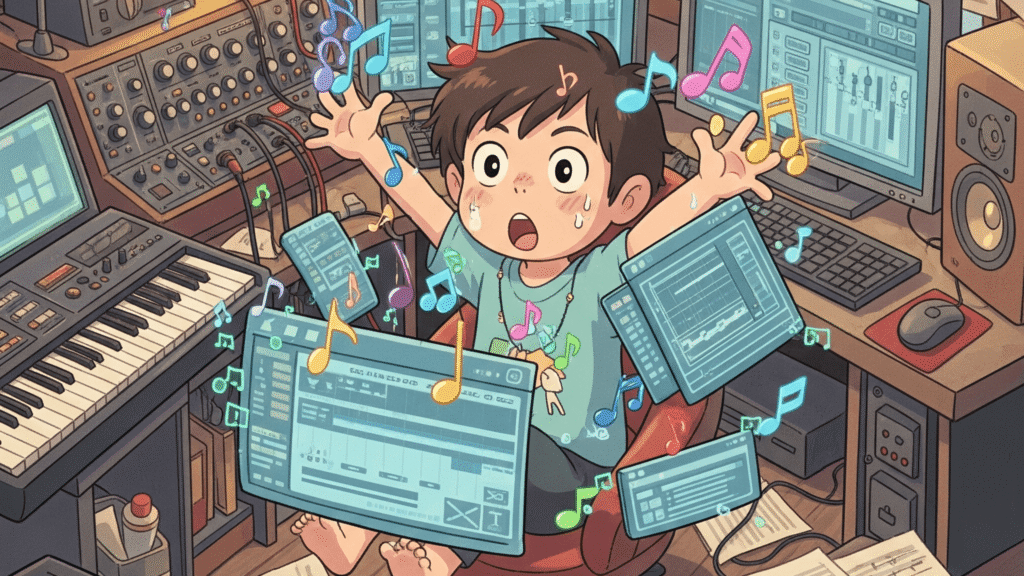
「無意識のパクリ」を避け、自分だけのDTMサウンドを追求するためには、効果的なインプットと、それを昇華させるアウトプットの質を高めることが不可欠です。ここでは、あなたの音楽的個性を輝かせるための具体的な方法をご紹介します。
多様なジャンルの音楽を聴く耳を育てる
特定のジャンルやアーティストの音楽ばかりを聴いていると、知らず知らずのうちにその型にハマりがちです。真のオリジナル性を育むためには、積極的に聴く音楽の幅を広げ、多様なジャンルに触れることが非常に重要です。
- 意識的に「苦手」を克服する: 普段聴かないジャズ、クラシック、民族音楽、エレクトロニカ、ヒップホップなど、あえて普段は聴かないジャンルを聴いてみましょう。最初はピンとこなくても、繰り返し聴くうちに新しい発見があるはずです。
- 「なぜこの音を使っているのか?」を考える: ただ聴くだけでなく、「この曲のメロディはなぜ心を揺さぶるのか?」「このベースラインはなぜこんなにグルーヴするのか?」といったように、構成や使われている音色、リズムパターンなどを意識して分析してみましょう。新しいジャンルでは、自分の知らない引き出しをたくさん見つけられるはずです。
- 歴史を遡る: 現代の音楽だけでなく、そのジャンルのルーツとなる古い音楽にも触れてみてください。音楽の進化の過程を知ることで、表面的な模倣ではない、深い理解と応用力が身につきます。
多様な音楽に触れることで、あなたの「音楽の引き出し」は飛躍的に増え、無意識に既存のフレーズをなぞってしまうリスクを減らし、より豊かなアイデアが生まれる土壌を育むことができます。
DTM以外の芸術からもインスピレーションを得る
音楽は、あらゆる芸術と繋がっています。DTMのインスピレーションを音楽だけに限定してしまうのはもったいないことです。音楽以外の芸術から刺激を受けることで、予想もしないようなアイデアや表現方法が生まれることがあります。
- 映画やアニメ: ストーリー、登場人物の感情、風景、照明の色など、視覚情報や物語から得られる感情は、楽曲のテーマやムード作りに直結します。「このシーンのBGMはどんな音だろう?」「このキャラクターの心情を表すメロディは?」と考えてみましょう。
- 絵画や写真: 色彩、構図、光の当たり方、描かれている情景から、特定の感情や雰囲気を捉え、それを音で表現する試みをしてみましょう。例えば、「この青い絵からどんな音が聞こえるか?」といった具合です。
- 文学(小説、詩): 言葉の持つリズム、情景描写、登場人物の感情の機微は、メロディの抑揚や歌詞のインスピレーションになります。特定の場面や一文から、曲のアイデアを膨らませてみてください。
- 自然: 風の音、波の音、鳥の声、雨の響きなど、自然界の音や風景は、リズムや音色のアイデアの宝庫です。
これらの活動は、あなたの感受性を豊かにし、DTMの表現の幅を格段に広げてくれるはずです。
定期的に自分の曲を客観視する習慣をつける
インプットを増やし、アイデアを形にしたら、最後に重要なのが「客観視」です。自分だけで完結せず、定期的に自分の曲を第三者の視点で評価する習慣をつけましょう。
- 時間を置く: 作曲中は夢中になり、客観的な判断が難しくなります。完成したと思っても、すぐに聴き返すのではなく、数日〜数週間時間を置いてから改めて聴いてみましょう。冷静な耳で聴くことで、「あれ、この部分、あの曲に似てるかも?」と気づいたり、改善点が見えたりすることがあります。
- 信頼できる人に聴いてもらう: 音楽仲間やDTMに詳しい友人など、信頼できる第三者にフィードバックを求めるのも有効です。自分では気づかない類似点や、改善すべき点を指摘してもらえるかもしれません。その際、「この曲、どこかに似ている部分はないか?」と具体的に質問してみるのも良いでしょう。
- 分析ツールの活用: 最近では、楽曲の類似性を分析するオンラインツールなども存在します(ただし、これはあくまで補助的なツールであり、法的な判断基準ではありません)。試してみることで、新たな気づきが得られる可能性もあります。
- 自己分析ノートを作る: 自分の曲の制作過程で「なぜこのコードを選んだのか」「なぜこのメロディになったのか」などを記録するノートを作るのも有効です。客観視する際に、自分の意図を再確認できます。
これらのインプットとアウトプットの習慣を身につけることで、「無意識のパクリ」のリスクを減らし、あなた自身の独創的な音楽スタイルを確立していくことができるはずです。ぜひ、今日から実践してみてくださいね!
\DTMの情報が沢山!上達も早くなる!/
著作権侵害の可能性をチェックするツールやサービス
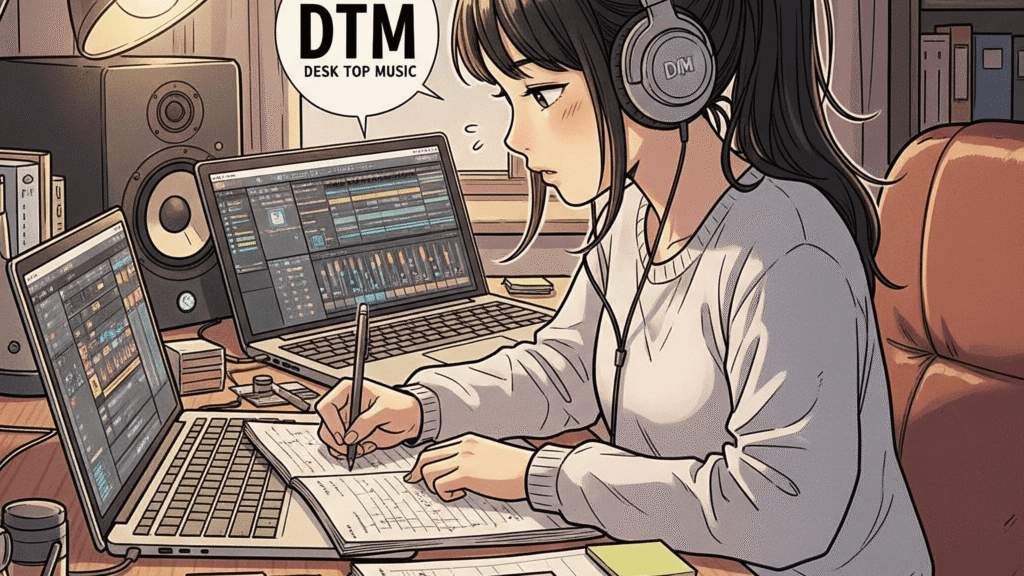
「これって本当にオリジナル?」と感じたとき、まず自分でできる確認方法として、類似性をチェックするツールやサービスの活用が挙げられます。
メロディー検索「弾いちゃお検索」:あなたのオリジナルを守る必須ツール
DTMで作曲をする際、「これって、もしかしてあの曲に似てる?」と不安になった経験はありませんか?意図せず既存の楽曲に似てしまう、いわゆる「無意識の類似」を防ぐために、ぜひ活用してほしいのが、ヤマハが提供する画期的なツール「弾いちゃお検索」です。
このツールは、あなたの大切なオリジナル楽曲を「無意識の類似」から守るための、まさに頼れる味方。私自身も楽曲制作の際に頻繁に利用しており、その精度の高さには驚かされています。
「弾いちゃお検索」とは?:メロディーの音階から類似曲を検出
「弾いちゃお検索」は、あなたが頭の中で思い描いた、あるいは打ち込んだメロディーの音階を入力するだけで、そのメロディーに似ている楽曲をヤマハの膨大な楽曲ライブラリから瞬時に探し出して表示してくれる優れものです。
使い方はいたってシンプル。直感的に操作できるため、DTM初心者の方でも迷うことなく利用できるでしょう。
驚きの精度!キーが違ってもしっかり検索
「弾いちゃお検索」の特筆すべき点は、その検索精度の高さにあります。特に画期的なのが、打ち込んだメロディーが移調されている場合でも、しっかりと類似する楽曲を検出してくれる点です。
例えば、Cメジャーで入力したメロディーが、他の曲ではGメジャーで使われていたとしても、同じメロディラインであればきちんと検索結果に表示されます。他にも似たようなメロディー検索アプリは存在しますが、この「キーが違っていても類似メロディーを見つけ出す」機能は、「弾いちゃお検索」ならではの大きな強みであり、多くのクリエイターにとって非常に心強い機能と言えるでしょう。
「無意識の類似」を未然に防ぐ習慣をつけよう
プロの作曲家は、日々締め切りに追われながら、膨大な数のメロディーを生み出し続けています。そんな多忙な制作活動の中で、ふと頭に浮かんだメロディーが、本当に「自分の頭の中から生まれたもの」なのか、それとも「どこかで聴いて記憶に残っていたメロディーの断片」なのかを、自分自身で判別するのは非常に難しい問題です。
だからこそ、「弾いちゃお検索」を日々の制作フローに組み込み、「類似予防」の習慣を身につけることが極めて大切です。制作したメロディーを世に出す前に一度「弾いちゃお検索」にかけることで、意図しないトラブルを未然に防ぎ、安心して作品をリリースできます。
- 音楽類似度分析サービス: オンライン上には、アップロードした楽曲と既存のデータベースを照合し、類似度を解析してくれるサービスがいくつか存在します。例えば、KENDRIXや著作権管理団体(JASRACなど)が提供しているデータベース検索機能や、音楽認識技術を応用したサービスなどです。これらのツールは、メロディラインやコード進行の似ている部分を特定するのに役立ちます。ただし、これらのツールが出す結果はあくまで参考情報であり、法的な判断を直接下すものではない点に注意が必要です。
- 耳コピでの徹底比較: もし、特定の曲に似ていると感じるなら、その曲と自分の曲を並行して聴き比べ、メロディ、リズム、コード進行、ハーモニー、構成などを細かく比較してみましょう。特に、メロディの音の動きやリズムパターン、特徴的なコードの響きがどの程度一致しているかを確認することが重要です。自分で楽譜に起こしてみるのも、視覚的に類似点を発見する助けになります。
- 多様なリスナーの意見を聞く: 信頼できる音楽仲間や、普段からDTM作品を聴き慣れている友人に、「この曲、どこかの曲に似てるかな?」と率直な意見を求めてみましょう。自分では気づかない客観的な視点を得られることがあります。ただし、あくまで個人の感想であるため、鵜呑みにせず参考程度に留めることが大切です。
これらのチェックは、あくまで初期段階のセルフチェックです。もし高い類似性が見つかった場合は、次のステップに進むことを検討しましょう。
専門家への相談も検討する
セルフチェックで「これはもしかしたらまずいかも……」と感じたり、法的な問題に発展する可能性があると判断したりした場合は、専門家への相談を検討するのが最も確実で安全な方法です。
- 著作権専門の弁護士: 音楽著作権に関する知識を持つ弁護士に相談すれば、法的な観点からあなたの楽曲と既存楽曲の類似性を評価してもらい、著作権侵害にあたる可能性や、その場合の対処法について具体的なアドバイスを得られます。費用はかかりますが、将来的なトラブルを避けるためには最も有効な手段です。
- 音楽著作権管理団体: JASRACなどの著作権管理団体に直接問い合わせてみるのも一つの方法です。著作権に関する一般的な情報や、疑義が生じた場合のフローについて教えてもらえる可能性があります。
- 音楽業界関係者: もし、音楽業界に詳しい知人やプロデューサーがいる場合は、彼らの意見を聞いてみるのも良いでしょう。業界の慣習や過去の事例から、実践的なアドバイスが得られるかもしれません。
「パクリかも?」という不安を抱えたまま作品を公開するのは、精神的にも負担が大きく、万が一トラブルになった際のリスクも伴います。早期に客観的な確認を行い、必要に応じて専門家の意見を求めることで、安心して音楽活動を続けることができるでしょう。
オリジナル曲を作る上で、既存の音楽から何らかの影響を受けることは自然なことです。大切なのは、その影響を「無意識の模倣」で終わらせず、独自のアイデアで昇華させ、責任を持って作品を世に出す姿勢です。
💡 【2025最新】Q&A:無意識の類似と著作権に関する疑問を解消

ここでは、DTMや作曲を行う上で多くの人が抱える「無意識の類似」や「著作権侵害のリスク」に関する疑問について、Q&A形式で解説します。あなたの創作活動の不安を解消し、安心して音楽制作に打ち込むための知識を提供します。
Q1. 無意識の類似でも著作権侵害として訴えられることはありますか?
A. 可能性はゼロではありません。日本の著作権法において、侵害が成立するためには「依拠性(既存の作品を知っていて、それに基づいて作ったこと)」と「類似性(表現形式が似ていること)」の両方が認められる必要があります。
無意識で制作した場合、通常は「依拠性」が認められにくいですが、極めて高い「類似性」があり、かつ公衆に触れる機会が多い楽曲(既存の有名曲など)との比較では、結果的に権利者から指摘を受けるリスクはあります。不安を煽るわけではありませんが、無意識であっても結果的に似ていれば問題に発展する可能性があるため、チェック体制を持つことが重要です。
Q2. どの程度似ていたら「盗作」や「パクリ」と判断されてしまうのでしょうか?
A. 法律上の判断基準は非常に複雑で、明確な「○小節以上似ていたらアウト」という基準はありません。主に以下の要素が重視されます。
- メロディの主要部分や特徴的なフレーズ:楽曲の核心となる部分が酷似している場合。
- 創作性の高い部分:その楽曲特有の表現方法や、オリジナリティの高い部分が一致しているか。
一方、一般的なコード進行(例:カノン進行)や、普遍的なリズムパターン、ジャンルに共通するありふれたフレーズなどは、著作権の保護対象外とされるケースが多いです。判断に迷う場合は、感情論ではなく、楽譜上で比較し、専門家の意見を聞くのが確実です。
Q3. 「オマージュ」として作ったつもりでも著作権侵害のリスクはありますか?
A. リスクはあります。オマージュは、元ネタに対する敬意を示す引用・表現ですが、著作権法上の「引用」のルール(公正な慣行に合致し、目的上正当な範囲で行うなど)を満たさなければなりません。
元ネタの楽曲の本質的な部分を無断で利用したり、引用部分が長すぎたりする場合、「オマージュ」として制作側の意図があっても、法的には無断利用(複製または翻案)と見なされる可能性があります。トラブルを避けるためには、インスピレーションを参考にしつつも、元の楽曲の表現形式から大きく離れた、新しい表現を生み出すことが不可欠です。
Q4. 自分の曲が既存曲に似ていないかチェックする方法は?
A. 著作権侵害のリスクを減らすために、以下の方法を組み合わせて客観的なチェックを行う習慣をつけましょう。
| チェック方法 | 特徴と利点 |
| ヤマハ「弾いちゃお検索」 | 自分の鼻歌や鍵盤演奏から、既存の楽曲データを検索可能。意図しない類似性の早期発見に有効です。 |
| 耳コピと楽譜比較 | 既存曲と自分の曲を並行して聴き比べ、特にサビやAメロの特徴的なフレーズを楽譜上で比較します。 |
| 信頼できる第三者の意見 | 音楽制作に関わっていない知人など、客観的な耳を持つ人に意見を聞くことで、自分の耳が慣れてしまったことによる判断ミスを防げます。 |
| 著作権専門の弁護士への相談 | 不安が強い場合や、大規模な商業利用を予定している場合は、著作権専門の弁護士に相談するのが最も確実です。 |
Q5. 類似性を避けて、オリジナリティの高い楽曲を制作するためのインプットは?
A. 無意識の類似性の多くは、インプットソースが偏っていることが原因で起こります。オリジナリティを高めるためには、あえて普段の習慣から離れたインプットが効果的です。
- 多様なジャンルに触れる:普段聴かないジャンルや、全く畑違いの国の音楽を聴くことで、新しいリズムやコード進行の組み合わせを発見できます。
- 音楽以外の芸術から学ぶ:映画、絵画、文学、写真集など、音楽とは異なる芸術作品から「感情の表現方法」や「構成の仕方」を学ぶことで、独自性のあるアイデアや世界観が生まれやすくなります。
- 「客観視」する習慣を持つ:制作後、しばらく曲を寝かせたり、DAWの画面を見ずに音だけを聴くなどして、常に客観視する習慣を持つことが、独創性を保つ上で重要です。
DTM作曲を手早く上達させたいならシアーミュージック

- 迅速で自由な予約システム
ウェブサイトや電話を通じて、レッスンの日程、時間、場所を自由に選んで簡単にご予約いただけます。 - 相性の良い講師の選択
学びたい内容やコースに合わせて、最適な講師を自由にお選びいただくことが可能です。 - ストレスフリーを保証する教室環境
当社の教室は、充実したレッスンが受けられるリラックスした雰囲気を保証しております。 - 特別講師:登録者200万人を誇るYouTuber「しらスタ」
特別講師として、登録者200万人を超えるYouTuber「しらスタ」が在籍しております。
シアーミュージックは、自由に楽しく上達したい大人の初心者に最適な音楽教室です。
この教室は、大人の初心者が失敗を恐れずに安心して音楽を楽しめるように運営しております。
- 講師との相性が合わない
- レッスンスケジュールを守るのが難しい
これらの問題を解決するため、シアーミュージックでは学びたい内容やジャンルに応じて、講師を固定せずに自由に選べるレッスンを提供しています。
まるで大学の講義を選ぶような感覚で、自分に合った講師を選ぶことができ、忙しい大人の方に配慮し、レッスンスケジュールも自分でカスタマイズ可能です。
更に、オンラインレッスンもあるので、固定されたスケジュールがプレッシャーになることを避け、より柔軟にレッスンを受けられます。

時間管理がしやすいのは、忙しい人にとってはありがたいね!
シアーミュージックは、コストパフォーマンスが高いく、迅速で自由な予約システムを通じて、各地域の分布バランスによる通いやすさと利便性を提供し、リラックスした教室環境で継続的にレッスンを受けることができます。
また、口コミと評価の高い講師陣から、学びたい内容に最適な講師を選ぶことができるため、上達を確実にサポート、質の高い指導を受けることができます。
| シアーミュージック概要 | |
|---|---|
| 運営 | シアー株式会社 |
| 対応楽器 | ・バイオリン・ピアノ・エレキギター・アコースティックギター ・ベース・ウクレレ・ドラム・サックス・DTM |
| レッスン料 | ・月2回 / ¥10,000(税込¥11,000)※1レッスン当たり税込5,500円 ・月3回 / ¥13,500(税込¥14,850)※1レッスン当たり税込4,950円 ・月4回 / ¥16,000(税込¥17,600)※1レッスン当たり税込4,400円【一番お得】 |
| レッスン時間 | 1コマ45分 ※入替/準備の時間含む |
| レッスン形態 | マンツーマンレッスン |
| レベル | 趣味嗜好の方からプロ志向の方まで |
| 入会金 | 2,000円(税込2,200円) |
| 校舎 | ・北海道・青森・秋田・盛岡・仙台 ・新潟・郡山・金沢・長野・東京都内・東京近郊 ・岐阜・静岡・愛知・大阪・兵庫・岡山・倉敷・福山 ・広島・松山・博多・小倉・福岡天神 ・熊本・鹿児島・那覇 ・オンライン |
| 無料特典 | ・練習室を無料でレンタル可能 ・楽器レンタル無料 ・無料体験教室 |
| 公式サイト | シアーミュージック |
\「シアーミュージック」を無料で体験してみる!/
まとめ:DTM作曲は「学ぶ」と「創造する」のバランスが重要!
ここまで、DTM作曲初心者が陥りやすい「無意識のパクリ」のメカニズムから、それを回避するための具体的な対策までを詳しく見てきました。最終的に、作曲活動において最も大切なのは、「学ぶこと」と「創造すること」のバランスだと私は考えます。
DTM作曲は「学ぶ」と「創造する」のバランスが重要!
音楽は、過去の偉大な作品の上に成り立っています。既存の曲を聴き、分析し、そこからインスピレーションを得る「学ぶ」行為は、あなたの音楽的基盤を築き、引き出しを増やす上で欠かせません。多様なジャンルに触れ、音楽以外の芸術からも刺激を受けることで、あなたの感性は磨かれ、創造の源泉はより豊かになるでしょう。
しかし、ただ学ぶだけでは「模倣」に終わってしまう可能性も秘めています。学んだ知識や得たインスピレーションを、いかに自分の中で消化し、「自分だけの音」としてアウトプットする「創造する」力が問われます。この創造の過程で、時には「弾いちゃお検索」のようなツールを活用し、客観的な視点を取り入れることも非常に有効です。
「パクリ」を恐れて作曲の手を止めてしまうのは、あまりにももったいないことです。大切なのは、著作権への理解を深め、自分の作品に責任を持つ意識を持つこと。そして、もし不安を感じたら、今回の記事で紹介した確認方法や対処法を試してみてください。
DTMは、無限の可能性を秘めたクリエイティブな活動です。学ぶことを楽しみ、創造することに情熱を注ぎながら、あなたにしか生み出せない素晴らしい音楽を世界に届けていきましょう!