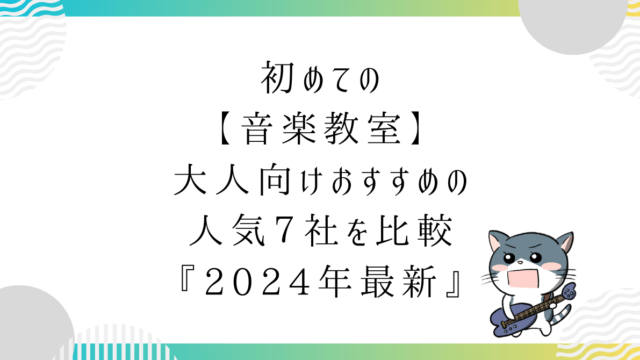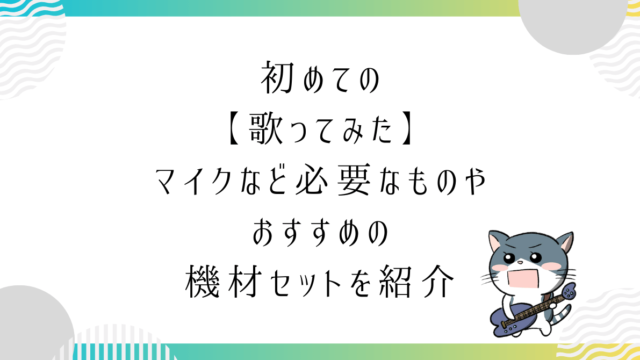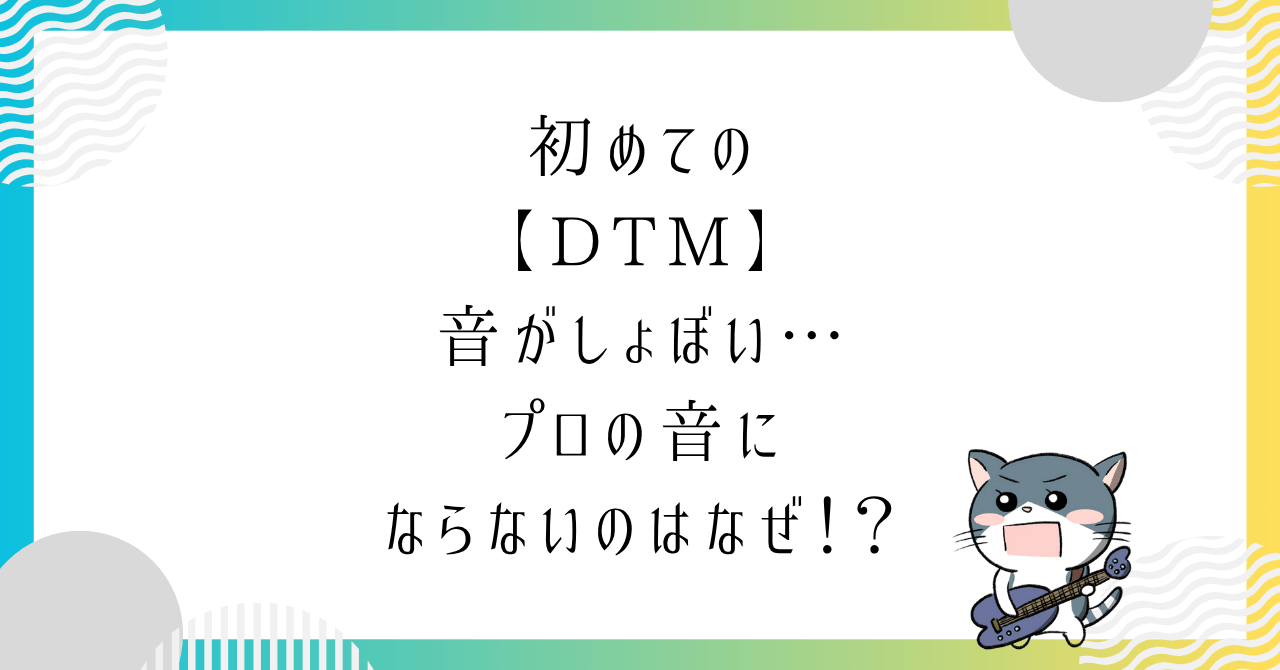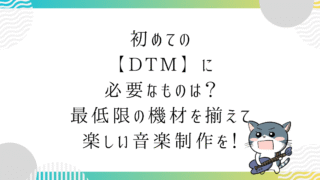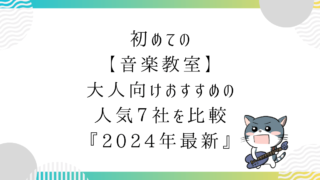DTM(デスクトップミュージック)を始めたばかりの方、あるいはDAWと睨めっこする日々を送っているあなた。せっかく時間と情熱を注いで作った曲なのに、「なんだか音がしょぼいな…」「プロの音と全然違う!」と感じて、モチベーションが下がってしまうことはありませんか?
安心してください、それはDTM初心者さん、いや、経験者でも誰もが一度はぶつかる壁なんです!なぜあなたの音が「しょぼく」聞こえるのか、その原因は意外なところに隠されているかもしれません。
このページでは、あなたが抱えるその悩みを解決するため、プロのサウンドに一歩でも近づくためのヒントを分かりやすく解説していきます。独学で試行錯誤することも素晴らしいですが、もし効率的にプロの技術を学びたい、最短で理想の音に近づきたいと考えるなら、DTMスクールの活用も非常に有用な選択肢となるでしょう。

専門知識がなくても大丈夫。DTMをもっと楽しく、もっとあなたの理想の音に近づけるために、一緒に学んでいきましょう!
\DTMの情報が沢山!上達も早くなる!/
【DTMあるある】プロの音にならない?音がしょぼい理由は?
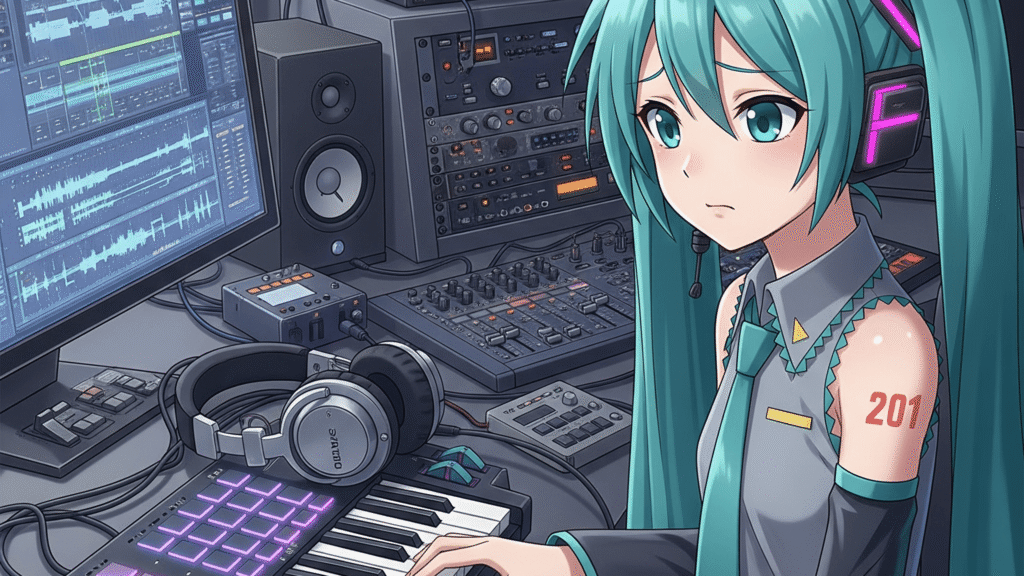
「なんでプロの曲はあんなに聴きやすいんだろう?」「自分の音源と何が違うの?」
DTMで曲を作っていると、そんな疑問にぶつかることがよくありますよね。特に初心者のうちは、頑張って作ったはずなのに、どこか音が「しょぼい」と感じてしまうものです。では、その「しょぼい音」の正体は何なのでしょうか? プロの音源との決定的な違いはどこにあるのでしょうか?
実は、プロの音とあなたの音源には、いくつかの見落としがちなポイントで差が出ていることがほとんどです。
- 音量バランスの悪さ: 各楽器の音量がバラバラで、聴きづらくなっていませんか? 特定の音が大きすぎたり、小さすぎたりすると、全体がまとまりなく聞こえてしまいます。
- 周波数帯域の衝突: それぞれの楽器が出す音が、同じ周波数帯でぶつかり合っていませんか? これが起こると、音が濁ったり、クリアさが失われたりします。
- 音圧の不足: 全体的な音量が小さく、迫力に欠けていませんか? ストリーミングサービスなどで他の曲と並べた時に、埋もれて聞こえてしまうことも。
- 空間表現の欠如: 音に奥行きや広がりがなく、平面的に聞こえていませんか? プロの音源は、リバーブやディレイなどを効果的に使って、音に豊かな空間を与えています。
- キレのなさ: ドラムやベースのアタックが弱く、グルーヴ感が足りないと感じることはありませんか? 音の立ち上がりや減衰が適切でないと、ノリが悪く聞こえてしまいます。
これらの要素が複雑に絡み合い、「しょぼい音」という印象を与えてしまうんです。でも大丈夫! これらの課題を一つずつクリアしていくことで、あなたのDTMサウンドは劇的に変わります。次に、具体的にどうすればプロの音に近づけるのか、その秘訣を探っていきましょう。
基礎が肝心!「良い音」を作るためのDTM基本設定
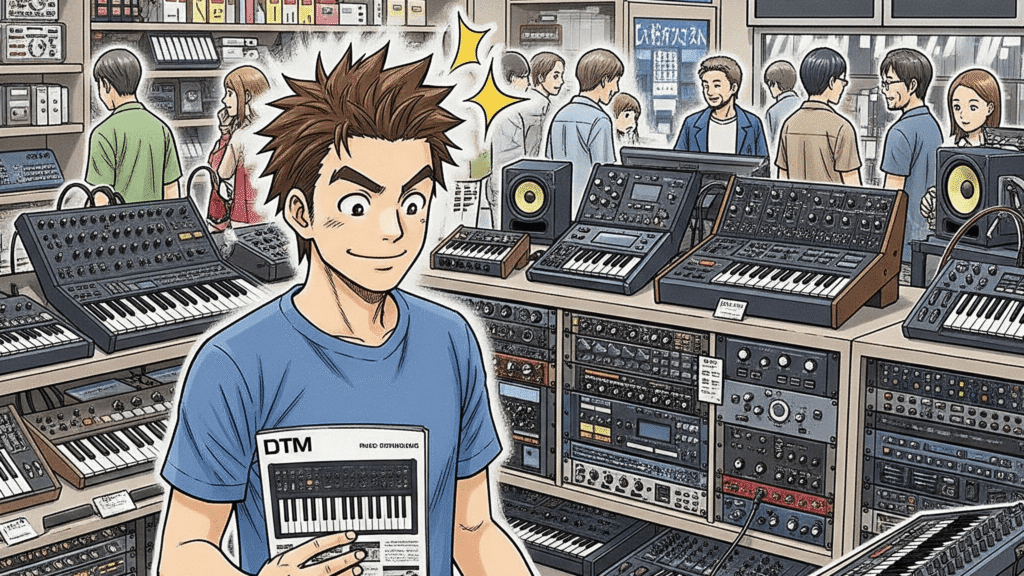
DTMでプロのようなクリアで迫力のあるサウンドを目指すなら、まず土台となる基本設定と環境の最適化が不可欠です。実は、音が「しょぼい」と感じる原因の多くは、この基礎部分にあります。適切な機材選びからDAWの設定、音源の選定まで、一つずつ丁寧に見直すことで、あなたのDTM環境は劇的に改善し、理想のサウンドに確実に近づけます。
DTM環境の最適化:PCスペックとオーディオインターフェース
良い音を作る第一歩は、安定したDTM環境を整えることです。
- PCスペックの重要性 DTMでは、複数の音源やエフェクトを同時に処理するため、ある程度のPCスペックが求められます。特に重要なのは、CPUの処理能力(Core i5以上、できればi7以上が推奨)とメモリ(RAM)の容量(最低8GB、16GB以上が理想)です。これらのスペックが不足していると、音が途切れたり、DAWの動作が重くなったりして、スムーズな作業ができません。快適なDTMライフのためにも、予算内でできる限り高性能なPCを選ぶことをおすすめします。
- オーディオインターフェースの導入 DTM初心者の方が見落としがちなのが、オーディオインターフェースの存在です。これは、PCとマイク、スピーカーなどを繋ぐ外部機器で、音の入出力に特化しています。PC内蔵のサウンド機能だけでは、音質が劣化したり、音の遅延(レイテンシー)が発生したりする原因になります。 オーディオインターフェースを導入することで、クリアなサウンドで音をモニタリングでき、録音時の音質も格段に向上します。また、遅延が抑えられるため、演奏と音のズレに悩まされることもなくなります。DTMの音質向上には、もはや必須アイテムと言えるでしょう。
DAWの基本設定と正しいゲイン管理
快適な作業環境が整ったら、次にDAW(Digital Audio Workstation)の基本設定を見直しましょう。
- DAWのサンプリングレートとバッファサイズ DAWには、音質に関わる重要な設定があります。
- サンプリングレート(Sampling Rate):音の滑らかさを決める数値で、一般的に44.1kHzまたは48kHzが推奨されます。数値が高いほど高音質になりますが、PCへの負荷も高まるため、まずはこのあたりから始めるのが良いでしょう。
- バッファサイズ(Buffer Size):音の遅延(レイテンシー)とPC負荷のバランスを取る設定です。録音時は遅延を抑えるために小さく(例:128サンプル)、ミックス・マスタリング時はPC負荷を減らすために大きく(例:512サンプル以上)すると効率的です。
- 正しいゲイン管理(ゲインステージング) 「音がしょぼい」と感じる原因で意外と多いのが、ゲイン管理の失敗です。ゲインとは、音の入力レベルのこと。 音源やプラグイン、各トラックのレベルが大きすぎると、音が割れたり(クリッピング)、ノイズが乗ったりして、一気に音が悪くなります。逆に小さすぎると、ノイズが目立ったり、次の工程でレベルを上げるときに音質が劣化する原因になります。 各トラックのピークレベルが-6dB~-10dB程度になるように調整し、DAWのマスターアウトがクリッピングしないよう常に意識しましょう。これは、後のミックス作業のしやすさにも直結する非常に重要なポイントです。
音源選びのコツ:有料プラグインは必要?
DTMを始めたばかりだと、「プロは高価な有料プラグインを使っているから良い音がするんだ」と思いがちですが、実はそうとは限りません。
- 無料・付属音源でも十分良い音は作れる DTMを始めたばかりの頃は、DAWに付属している音源や、インターネットで手に入る無料の音源・プラグインでも十分にクオリティの高いサウンドを作ることが可能です。まずは、それらの音源の特性を理解し、使いこなす練習をしましょう。基本的な音作りやエフェクト処理のスキルが身につけば、無料のものでも驚くほど良い音が出せるようになります。
- 有料プラグインを導入するタイミング 有料プラグインは、特定の音色や機能、より高度な音作りを追求したいときに検討するものです。例えば、「特定の楽器の音がどうしても安っぽい」「もっとリアルなドラム音が欲しい」といった具体的な課題が見つかったときに、その課題を解決できるプラグインを探すのがおすすめです。 焦って高価なものを購入するよりも、まずは既存のツールを最大限に活用し、「なぜこの音が悪いのか」「どうすれば改善できるのか」を考えることが、音作りのスキルアップに繋がります。
これらの基礎をしっかりと押さえることで、あなたのDTMサウンドは着実にプロの音に近づきます。焦らず、一つずつ丁寧に設定を見直していきましょう。
ミックスで劇的変化!プロの音に近づけるための秘訣
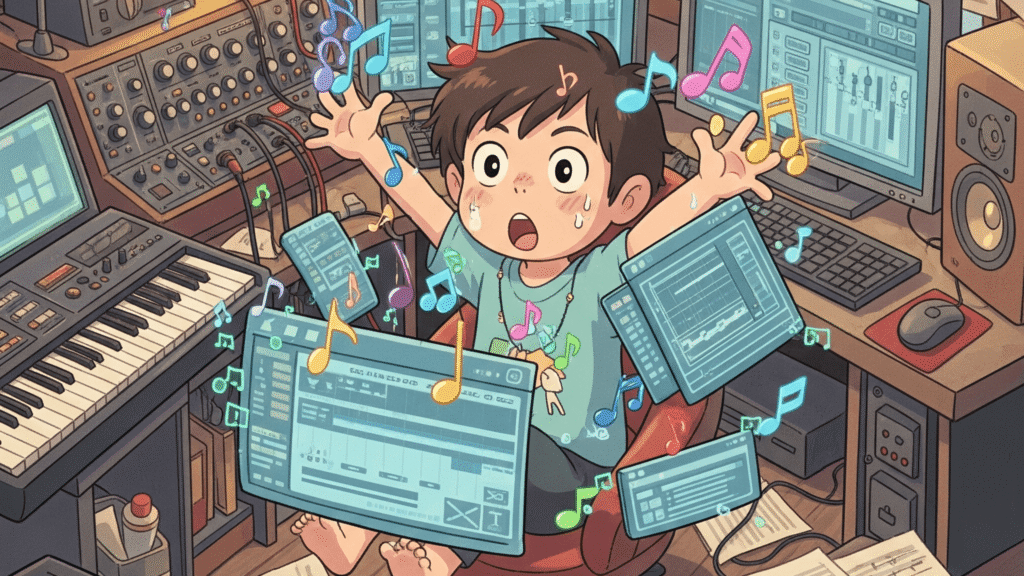
DTMの楽曲制作において、音が「しょぼい」と感じる主な原因の一つは、ミックスの甘さにあることがほとんどです。しかし、安心してください!EQ(イコライザー)、コンプレッサー、リバーブ・ディレイ、そして音量バランスとパンニングといった基本的なツールを適切に使いこなすことで、あなたのトラックは劇的に変化し、プロの音源のようなクリアさと迫力を手に入れることができます。これらのテクニックは、一見複雑そうに見えますが、それぞれの役割を理解し、実践することで、あなたのDTMスキルは飛躍的に向上します。
EQ(イコライザー)の基本と実践テクニック
EQは、音の周波数バランスを調整し、それぞれの音が持つ特徴を引き出したり、不要な部分をカットしたりするための強力なツールです。
- EQの基本:音の不要な部分をカットする「引き算」 EQの最も重要な役割は、音を良くすることよりも、音を悪くしている部分を取り除くことにあります。例えば、ベースやキックのトラックにこもった低域が、他の楽器のクリアさを邪魔していることがあります。これをEQでカットすることで、全体の音がスッキリし、各楽器の音が際立つようになります。まずは、不要な低域や中域の「濁り」をカットすることから始めてみましょう。
- 実践テクニック:楽器同士の帯域の住み分け 複数の楽器が鳴っているとき、同じ周波数帯で音がぶつかり合うと、互いの音を邪魔してしまいます。例えば、ボーカルとギターが中域で衝突している場合、それぞれの楽器の特性に合わせて、少しずつ周波数帯をずらしてみましょう。ボーカルのクリアさが欲しいなら、ボーカルが目立つ周波数帯を少し持ち上げつつ、その帯域でギターを少し下げる、といった調整が効果的です。これにより、各楽器がそれぞれの「居場所」を見つけ、ミックス全体がクリアになります。
コンプレッサーで音に「パンチ」と「まとまり」を出す
コンプレッサーは、音の大小の幅(ダイナミクス)を調整し、音にパンチを与えたり、全体のまとまりを出すために使われるエフェクトです。
- コンプレッサーの基本:音量の均一化とアタック感の調整 コンプレッサーは、大きな音を抑え、小さな音を持ち上げることで、音量差を縮めます。これにより、音が安定し、聴きやすくなります。ドラムのスネアやキックに使うと、アタック感(音の立ち上がり)が強調され、より力強く、パンチのあるサウンドになります。また、ボーカルにかけることで、歌声の音量が安定し、常にクリアに聴こえるようになります。
- 実践テクニック:バスコンプで全体のグルーヴを統一 個々のトラックにかけるだけでなく、ドラム全体やボーカルグループ、さらにはミックス全体にバスコンプレッサーを使うことも非常に効果的です。これにより、各トラックがバラバラに鳴っている状態から、まるで一つの楽器が鳴っているかのように一体感が生まれます。特にドラムにバスコンプをかけると、グルーヴがまとまり、よりプロフェッショナルなサウンドに近づきます。
リバーブ・ディレイで空間を彩る
リバーブ(残響)とディレイ(やまびこ)は、音に奥行きや広がりを与え、楽曲に豊かな空間を創造するためのエフェクトです。
- リバーブの基本:自然な空間を演出 リバーブは、まるで音が部屋の中で響いているかのような残響をシミュレートします。ボーカルやアコースティック楽器に少し加えるだけで、音が乾燥した印象から、自然な空気感を帯びた豊かなサウンドに変わります。かけすぎると音がぼやけてしまうので、まずは控えめに、楽曲全体に馴染むように調整することが大切です。
- ディレイの基本:音に広がりとリズム感を与える ディレイは、音が繰り返して聞こえる効果を生み出します。ボーカルのフレーズの終わりに軽くかけると、余韻が残り、印象的な演出ができます。また、シンセパッドやギターのリズムに合わせてディレイをかけることで、音に広がりとリズム感を与え、楽曲全体をよりダイナミックにすることができます。
各トラックの音量バランスとパンニングの重要性
これまでのエフェクト処理も大切ですが、最終的にプロの音に近づけるためには、各トラックの音量バランスと、左右の音の配置を決めるパンニングが非常に重要です。
- 音量バランス:すべての基本中の基本 ミックスで最も重要なのが、各トラックの音量バランスです。どんなに良い音作りをしても、音量バランスが崩れていれば、全体が聴きづらくなります。まずは、すべてのフェーダーをゼロに戻し、一番聴かせたい音(通常はボーカルやメインのメロディ楽器)から音量を決め、それに合わせて他の楽器の音量を調整していくと良いでしょう。楽曲の構成や展開に合わせて、音量を細かくオートメーションで調整することも忘れずに。
- パンニング:音の広がりと分離感を演出 パンニングは、各楽器を左右のどの位置に配置するかを決める作業です。例えば、ドラムセットであれば、ハイハットは右に、タムは左に、といった具合に実際の楽器の配置を意識してパンニングすることで、立体感が生まれます。また、ボーカルは中央に、ギターは左右に広げるなど、各楽器に適切な「居場所」を与えることで、音がぶつかり合うのを防ぎ、分離感が向上し、よりクリアで奥行きのあるサウンドになります。
これらのミックステクニックは、DTM制作の腕を上げる上で避けては通れない道です。一つずつ丁寧に取り組むことで、あなたの楽曲は間違いなく「しょぼい音」から卒業し、プロの音源に負けないクオリティへと進化するでしょう。
マスタリングで仕上げ!音圧とクリアさを手に入れる
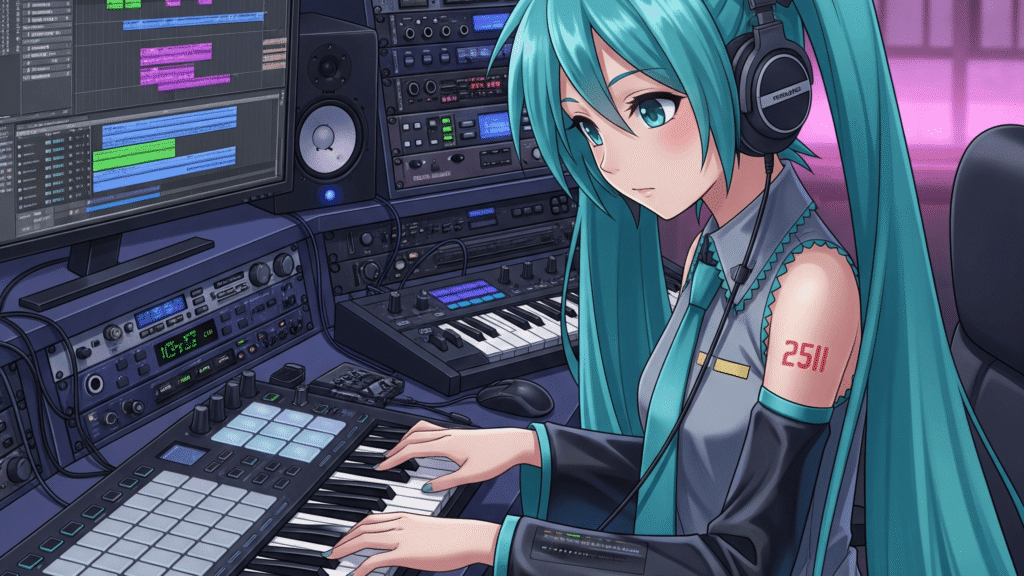
ミックス作業を経て、各楽器のバランスが整い、クリアなサウンドになったら、いよいよ楽曲の最終工程であるマスタリングです。マスタリングは、楽曲全体の音圧を上げ、あらゆる再生環境で最高の音質を保つための重要なプロセス。まるで写真の「最終レタッチ」のように、楽曲に最後の輝きを与え、プロの作品として通用するレベルに引き上げます。ここで、あなたの「しょぼい音」は完全に卒業し、世に送り出すにふさわしい音圧とクリアさを手に入れることができるでしょう。
マスタリングの目的と基本の流れ
マスタリングとは、ミックスが完了した「2mix(ステレオファイル)」に対して行う最終調整のこと。主な目的は以下の3点です。
- 音圧の最適化: 他の商業楽曲と並べても遜色ない音量・迫力を与えること。
- 音質の均一化: 楽曲全体の周波数バランスを整え、特定の帯域が突出したり、不足したりしないように調整すること。
- 再生環境への対応: スマートフォン、カーオーディオ、大型スピーカーなど、どんな環境で聴いても良い音に聞こえるように最適化すること。
基本的なマスタリングの流れは以下のようになります。
- EQ(イコライザー): 楽曲全体の周波数バランスを最終調整。ミックスで取りきれなかった不要な響きをカットしたり、足りない帯域をブーストしたりします。
- コンプレッサー: 楽曲全体のダイナミクスを整え、音の粒立ちを揃えます。特に「バスコンプレッサー」を使って、楽曲に一体感とグルーヴを与えます。
- リミッター: 最終的な音圧を稼ぐために使用します。音のピークを抑え込み、音割れせずに全体の音量を持ち上げます。
これらの工程を経て、あなたの楽曲はプロ仕様のサウンドへと生まれ変わるのです。
リミッターとマルチバンドコンプレッサーの効果的な使い方
マスタリングにおいて、特に効果的なのがリミッターとマルチバンドコンプレッサーです。これらを使いこなすことで、音圧とクリアさの向上を両立できます。
- リミッター:音圧を最大限に引き出す最終兵器 リミッターは、設定した音量(スレッショルド)を超えた音を完全に抑え込むエフェクトです。マスタリングの最終段階で、音圧を稼ぐために使用します。
- 使い方: まず、リミッターの**アウトプットシーリング(Output Ceiling)**を-0.3dB〜-0.5dB程度に設定します。これは、音割れを防ぐための安全マージンです。次に、**スレッショルド(Threshold)**を徐々に下げていき、楽曲全体の音量が目的のレベルに達するまで調整します。メーターを見ながら、過度にリミッターがかかりすぎて音が不自然にならないように注意しましょう。
- ポイント: リミッターは強力なツールであるため、かけすぎると音が潰れたり、歪んだりしてしまいます。自然な音圧を得るためには、ミックス段階でしっかり音量バランスを整え、リミッターに過度な負担をかけないことが重要です。
- マルチバンドコンプレッサー:周波数帯域ごとのダイナミクスを制御 通常のコンプレッサーが楽曲全体(またはトラック全体)の音量差を調整するのに対し、マルチバンドコンプレッサーは、特定の周波数帯域ごとにコンプレッションをかけることができます。これにより、より繊細でピンポイントな音質調整が可能になります。
- 使い方: 例えば、低域が暴れて全体を濁らせている場合、低域のバンドにだけコンプレッサーをかけることで、その帯域だけをタイトに制御できます。高域が耳に刺さる場合は、高域のバンドを抑えることで、クリアさを保ちつつ聴き心地を良くすることができます。
- ポイント: 各周波数帯域の音量やダイナミクスの問題を解決するのに非常に有効ですが、慣れないうちは設定が難しいかもしれません。まずは、楽曲全体を聴いて、「どの帯域の音が問題か」を特定することから始め、その帯域にのみコンプレッションをかけてみましょう。繊細な調整が求められるため、少しずつ試しながら耳で判断することが重要です。
マスタリングは、あなたの楽曲をプロのクオリティへと引き上げる最終ステップです。これらのツールを効果的に使いこなすことで、あなたのサウンドは「しょぼい」という印象から解放され、リスナーの心に響く素晴らしい作品となるでしょう。
【2025最新】DTMの「音」に関するよくある質問(Q&A)

DTMを始めたばかりの頃は、専門用語や機材の多さに戸惑うものですよね。ここでは、多くの初心者がぶつかる疑問について、2025年現在の音楽制作シーンを踏まえた最新の回答をお届けします。
Q1. 無料のプラグインだけでプロっぽい音は作れるの?
A. はい、十分に可能です! 2025年現在、無料プラグインの質は飛躍的に向上しています。例えば、オーケストラ音源の「Spitfire Audio LABS」や、高性能EQの「TDR Nova」などは、プロの現場でも併用されるほどのクオリティです。 大切なのは「ツール」よりも「使い方(耳の鍛え方)」です。まずは無料版でミックスの基礎を学び、限界を感じた時に有料版へステップアップするのが、最も効率的な上達方法ですよ。
Q2. iZotopeなどのAIアシスト製品は初心者でも使いこなせる?
A. 非常に扱いやすいですが、「丸投げ」は禁物です。 iZotopeの「Ozone」や「Neutron」に搭載されているAIアシスト機能は、初心者にとって強力な味方になります。ボタン一つで「ある程度の正解」を提示してくれるからです。 ただし、AIが提案した設定に対して「なぜこの数値になったのか?」を考える習慣をつけることが大切です。iZotope公式のチュートリアルなどを併用して基礎知識を補うと、さらに一歩先のサウンドを目指せますよ。
Q3. DTMスクールって本当に必要?独学じゃダメなの?
A. 独学でも可能ですが、「時間をお金で買う」という視点ではスクールが有利です。 YouTubeやブログで情報は溢れていますが、自分に足りない知識をピンポイントで見つけるのは時間がかかります。 例えば「シアーミュージック」のようなスクールは、プロから直接フィードバックをもらえるため、挫折しにくい環境が整っています。最短距離でプロ基準の音作りを身につけたい方や、一人だとモチベーション維持が難しい方には、有力な選択肢の一つと言えますね。
Q4. 最初のオーディオインターフェース、どれを選べばいい?
A. 安定性と定番モデルを基準に選ぶのが失敗しないコツです。 2025年現在でも、初心者の方には以下の2モデルが圧倒的な支持を得ています。
- Steinberg UR22C: 動作の安定性が抜群で、Cubase AIが付属する。
- Focusrite Scarlett 2i2: 音に艶があり、多くのヒット曲制作で使用されている。 どちらも公式サポートが充実しており、トラブルの際もネット上に解決策が多いのがメリットです。
Q5. ミックスとマスタリングの違いを分かりやすく教えて!
A. 「料理」に例えると非常に分かりやすくなりますよ。
- ミックス: 野菜やお肉(各トラック)の火の通り具合や味付けを調整して、一つの皿に盛り付ける作業です。
- マスタリング: 盛り付けた料理を、お店のメニューとして最高の状態にパッケージングする最終工程です。音量バランスを整え、どの再生環境(スマホや車、クラブなど)でも最高の音で聴こえるように調整します。
ミックス前に確認すべき!5つのチェックリスト
「音が薄い」「迫力がない」と感じたら、以下のポイントを順に確認してみましょう。
- ゲインステージング: 各トラックの音が割れて(クリップして)いませんか?
- 引き算のEQ: 不要な低域(ローカット)を適切に行い、音の濁りを取っていますか?
- 定位(パン): すべての音が真ん中に集まりすぎて、空間が狭くなっていませんか?
- リバーブの量: 空間系をかけすぎて、芯のないボヤけた音になっていませんか?
- リファレンス: 憧れのプロの楽曲と、自分の曲を交互に聴き比べていますか?
まとめ:今日の一歩が、未来の名曲を生み出す DTMは覚えることが多い分、思い通りの音が出た時の喜びは格別です。あなたの音楽が誰かの心を動かす日を目指して、一つひとつの工程を楽しんでいきましょう。
DTMを手早く上達させたいならシアーミュージック

- 迅速で自由な予約システム
ウェブサイトや電話を通じて、レッスンの日程、時間、場所を自由に選んで簡単にご予約いただけます。 - 相性の良い講師の選択
学びたい内容やコースに合わせて、最適な講師を自由にお選びいただくことが可能です。 - ストレスフリーを保証する教室環境
当社の教室は、充実したレッスンが受けられるリラックスした雰囲気を保証しております。 - 特別講師:登録者200万人を誇るYouTuber「しらスタ」
特別講師として、登録者200万人を超えるYouTuber「しらスタ」が在籍しております。
シアーミュージックは、自由に楽しく上達したい大人の初心者に最適な音楽教室です。
この教室は、大人の初心者が失敗を恐れずに安心して音楽を楽しめるように運営しております。
- 講師との相性が合わない
- レッスンスケジュールを守るのが難しい
これらの問題を解決するため、シアーミュージックでは学びたい内容やジャンルに応じて、講師を固定せずに自由に選べるレッスンを提供しています。
まるで大学の講義を選ぶような感覚で、自分に合った講師を選ぶことができ、忙しい大人の方に配慮し、レッスンスケジュールも自分でカスタマイズ可能です。
更に、オンラインレッスンもあるので、固定されたスケジュールがプレッシャーになることを避け、より柔軟にレッスンを受けられます。

時間管理がしやすいのは、忙しい人にとってはありがたいね!
シアーミュージックは、コストパフォーマンスが高いく、迅速で自由な予約システムを通じて、各地域の分布バランスによる通いやすさと利便性を提供し、リラックスした教室環境で継続的にレッスンを受けることができます。
また、口コミと評価の高い講師陣から、学びたい内容に最適な講師を選ぶことができるため、上達を確実にサポート、質の高い指導を受けることができます。
| シアーミュージック概要 | |
|---|---|
| 運営 | シアー株式会社 |
| 対応楽器 | ・バイオリン・ピアノ・エレキギター・アコースティックギター ・ベース・ウクレレ・ドラム・サックス・DTM |
| レッスン料 | ・月2回 / ¥10,000(税込¥11,000)※1レッスン当たり税込5,500円 ・月3回 / ¥13,500(税込¥14,850)※1レッスン当たり税込4,950円 ・月4回 / ¥16,000(税込¥17,600)※1レッスン当たり税込4,400円【一番お得】 |
| レッスン時間 | 1コマ45分 ※入替/準備の時間含む |
| レッスン形態 | マンツーマンレッスン |
| レベル | 趣味嗜好の方からプロ志向の方まで |
| 入会金 | 2,000円(税込2,200円) |
| 校舎 | ・北海道・青森・秋田・盛岡・仙台 ・新潟・郡山・金沢・長野・東京都内・東京近郊 ・岐阜・静岡・愛知・大阪・兵庫・岡山・倉敷・福山 ・広島・松山・博多・小倉・福岡天神 ・熊本・鹿児島・那覇 ・オンライン |
| 無料特典 | ・練習室を無料でレンタル可能 ・楽器レンタル無料 ・無料体験教室 |
| 公式サイト | シアーミュージック |
\「シアーミュージック」を無料で体験してみる!/
まとめ:DTMは奥深い!良い音への道のりは続く
DTMで「しょぼい」と感じていた音が、この記事を通して少しでも「プロの音」に近づくヒントになったなら幸いです。ここまで解説してきたように、良い音を作るには、基礎的な環境設定から始まり、ミックス、そしてマスタリングという各工程での丁寧な作業が不可欠です。しかし、これらのテクニックはあくまで道具であり、最も大切なのはあなたの耳と、音に対する探究心だということを忘れないでください。
DTMの音作りは、まさに奥深い旅のようなもの。一度完璧な音が出せたと思っても、また新しい課題が見つかったり、時代とともに音のトレンドが変わったりと、常に学びと発見があります。今日身につけた知識は、その長い道のりのほんの始まりに過ぎません。
焦る必要はありません。大切なのは、楽しみながら、少しずつでも改善を重ねていくことです。様々な曲を聴き、どんな音が良いと感じるのかを分析したり、他のDTMerの作品からインスピレーションを得たりするのも良いでしょう。
この情報が、あなたのDTMライフをより豊かにする一助となれば幸いです。良い音を追求する旅はこれからも続きますが、きっとその先に、あなたの理想とするサウンドが待っているはずです。
さあ、これからも一緒に、DTMの奥深い世界を楽しみ尽くしましょう!